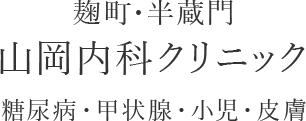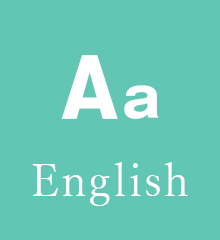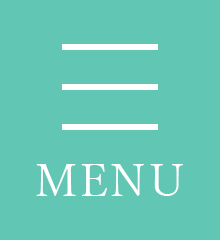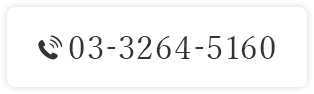心地よく寝られていますか?
昼間にやたら眠い方は
ご相談ください
以下の症状が当てはまる場合、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。
お早めに当院までご相談ください。
- 睡眠中に何度も呼吸が止まる・
浅くなる - 頻繁に目が覚めることがある
- 大きないびきをかく
- 息を求めてうめくような声を発する
- 昼間に疲労感や強い眠気を感じる
- 朝起きた時、頭痛がある
- 集中力が下がった
など
Menu
睡眠時無呼吸症候群とは
 睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に無呼吸または低呼吸になる状態です。「無呼吸」は、その名の通り、呼吸が止まる状態で、気道の空気の流れが止まる「気流停止」が、10秒以上ある状態とされています。一方で、呼吸が浅くなる状態は「低呼吸」と言います。
睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に無呼吸または低呼吸になる状態です。「無呼吸」は、その名の通り、呼吸が止まる状態で、気道の空気の流れが止まる「気流停止」が、10秒以上ある状態とされています。一方で、呼吸が浅くなる状態は「低呼吸」と言います。
このうち、気流停止が7時間以上の睡眠中に30回以上、または1時間につき5回以上あると、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。
症状は眠っている間に現れるため、ご本人が自覚することはほとんどありません。よって、ご家族の指摘によって気付くケースも珍しくありません。
睡眠時無呼吸症候群になると、質の高い睡眠がとれなくなり、昼間に強い眠気に襲われたり集中力が下がったりする恐れがあります。また、低酸素血症へのリスクが高まったり、交感神経の刺激が強まることで、心臓病や脳卒中の発症リスクが上昇したりします。
実際に睡眠時無呼吸症候群の方は、高血圧や心不全、不整脈などを併発しているケースが多い傾向にあります。
睡眠時無呼吸症候群の種類
睡眠時無呼吸症候群は別名(SAS)とも呼ばれ、主に閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)と中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)に分類されます。一般的な症例は閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)で、特徴としては睡眠中の大きないびきやうなり声が挙げられます。
閉塞性睡眠時無呼吸症候群
OSAS)
OSASでは、寝ている間に気道が上手く確保されず、無呼吸に陥ります。首や喉周りの脂肪、扁桃腺の肥大、軟口蓋や口蓋垂の腫れによって気道が閉塞されること、舌根の沈下などにより、無呼吸・低呼吸状態に陥ります。
中枢性睡眠時無呼吸症候群
(CSAS)
CSASは、気道自体は確保されているのにもかかわらず、脳からの呼吸指令がないために無呼吸に陥るタイプです。
睡眠時無呼吸症候群の症状
眠っている間に起こる無呼吸や低呼吸が主な特徴となりますが、ひどいいびきや唸り声なども挙げられます。ところが、患者様ご本人は眠っているため自覚せず、身近な方に指摘されて気付くことがあります。
その他にも、夜中にトイレに行く回数や寝汗が増えるといった症状も見られます。睡眠の量・質が十分でないことから、睡眠不足に陥り、昼間に深刻な眠気に襲われることもあります。また、頭痛や注意力低下、疲労感、抑うつ、性欲減退などの症状が生じることもあります。
睡眠時無呼吸症候群の原因
閉塞性の原因としては、肥満や過剰なストレスにより、気道が閉塞することが挙げられます。肥満により、首や喉周りに脂肪が蓄積されることや、扁桃の肥大、舌のサイズ・形状、耳鼻関連の疾患、顎の大きさなどが要因となり得ます。
睡眠時無呼吸症候群の検査
簡易検査
検査機器を使用して、就寝中の呼吸や血液中の酸素飽和度をご自宅で計測します。ご自宅での検査なので、入院は不要です。指示に従い、装置を顔と手に取り付けてご自宅で就寝していただきます。1時間あたりの無呼吸・低呼吸の平均回数が示される「無呼吸低呼吸指数」をご確認いただけます。
ポリソムノグラフィー検査
(PSG)
簡易検査で診断が難しい場合には、より詳細な検査を行います。ご自宅でPSG機器を装着し、必要と判断された方には入院検査も実施します。その際には、受診可能な医療施設へのご紹介も行います。主に、酸素飽和度や脳波をはじめ、眼球運動、呼吸、いびき、呼吸運動、心電図、姿勢などを詳細に調べます。
睡眠時無呼吸症候群の治療
(CPAP)
CPAP療法
 専用装置を付けて眠りにつくことで気道のスペースを作り、寝ている間に起こる無呼吸・低呼吸を防ぐ方法です。なお、CPAP療法は根本的な解決策ではありませんので、当院では減量など他の治療法と組み合わせて改善を目指します。
専用装置を付けて眠りにつくことで気道のスペースを作り、寝ている間に起こる無呼吸・低呼吸を防ぐ方法です。なお、CPAP療法は根本的な解決策ではありませんので、当院では減量など他の治療法と組み合わせて改善を目指します。
マウスピース
無呼吸・低呼吸が軽度で、かつ顎の位置などが原因だった場合には、マウスピースの治療を選択することがあります。ただし、中程度から重度の症状には有効ではありません。マウスピースを付けることで、気道を確保していくことができます。マウスピースの作成に際しては、睡眠時無呼吸症候群の治療に精通した歯科医に相談してください。
外科手術治療
扁桃腺やアデノイド組織の肥大によって睡眠中に起こる無呼吸・低呼吸を招いていた場合には、摘出手術を提案します。
その他の治療
(生活習慣の改善など)
肥満により喉・首の周りに脂肪が蓄積し、気道が塞がれて睡眠中に無呼吸・低呼吸が生じるケースがあります。その場合は、まず体重の管理や減量を行うことで、症状の改善を目指します。
この取り組みは、生活習慣病の予防にも繋がります。また、過度の飲酒は無呼吸や低呼吸の症状を悪化させる恐れがあります。食事、運動、飲酒、睡眠などの生活習慣を改善することは、症状の緩和において極めて有効とされています。
睡眠時無呼吸症候群の合併症
 代表的なものとして、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が挙げられます。特に動脈硬化が進行しやすく、それに伴い、心疾患や脳血管疾患といった深刻な疾患のリスクが高まります。通常は睡眠中、心臓は静かに動いていますが、睡眠時無呼吸症候群の場合は、熟睡中でも心臓が激しく動き続けてしまうため、心臓への負担も大きくなります。
代表的なものとして、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が挙げられます。特に動脈硬化が進行しやすく、それに伴い、心疾患や脳血管疾患といった深刻な疾患のリスクが高まります。通常は睡眠中、心臓は静かに動いていますが、睡眠時無呼吸症候群の場合は、熟睡中でも心臓が激しく動き続けてしまうため、心臓への負担も大きくなります。
高血圧
睡眠時無呼吸症候群の方々は、通常の方よりも、高血圧を発症する確率が2〜3倍にも増加します。睡眠時無呼吸症候群の治療により症状が良くなると、血圧管理にも効果が見られる傾向があります。
心不全
睡眠時無呼吸症候群の場合、睡眠中に胸腔内圧が低下し、心臓に負担がかかるため、心臓や血管系の疾患のリスクが上昇します。また、睡眠時無呼吸症候群を併発している慢性心不全の方は、30〜40%の割合であると報告されています。
不整脈
無呼吸から呼吸再開などのタイミングで、不整脈が起こるケースがあります。睡眠時無呼吸症候群の患者様は、心臓の拍動が安定しにくいため、不整脈を招く恐れがあります。
軽度の不整脈は様子を見るだけで済むこともありますが、命に影響を及ぼす深刻な不整脈も存在します。症状でお悩みの場合は、お早めにご相談ください。
心血管疾患
(心筋梗塞・狭心症・脳卒中)
睡眠時無呼吸症候群を発症すると、虚血性心疾患のリスクが2〜3倍も、脳卒中の発症リスクが2倍も上昇すると指摘されています。
無呼吸・昼間の眠気・いびき
に関するよくある質問(FAQ)
いびきや昼間の眠気の原因は何ですか?
「日中、眠気が強くて我慢できない」場合、その原因は多岐にわたります。抗アレルギー薬や鎮痛剤などの薬によるもの、甲状腺機能の低下、低血圧、うつ病などの疾患が原因となっているケースもあります。また、睡眠が十分に取れなくなる睡眠不足症候群であることも少なくありません。
実は、物理的な1日は24時間ですが、人の体内時計の1日は25時間とズレがあります。このズレの調整が上手くできず、睡眠時間がずれてしまう、概日リズム睡眠障害や睡眠時無呼吸症候群、じっとしていると足がむずむずして眠れなくなるレストレスレッグス症候群などにより、夜間の睡眠不足に悩む方もいます。
また、覚醒している状態で必要な脳内物質のオレキシンを作り出す細胞が機能しなくなり、何らかのきっかけで睡眠発作を引き起こすナルコレプシーという疾患も有名です。実際に日本では500人~1000人に1人、ナルコレプシーを発症しているのではないかと報告されています。
無呼吸によるいびきで昼間に眠気が出るって本当ですか?
睡眠時無呼吸症候群でなくても、いびきをかく方は、そうでない方よりも昼間の眠気の傾向が高くなることが報告されています。そして、いびきが激しいほど、昼間の過眠が強い可能性も示唆されています。
現時点では、いびきと昼間の過眠の関係は、完全に解明されているわけではありません。ただし、いびきをかくことは、気道のどこかで空気の通り道が狭くなっており、無理に空気を送り込もうとすることが原因とされています。肺に十分な量の空気が取り込まれないと、血中酸素が不足し、血中炭酸ガスが上昇します。その結果、化学的刺激による覚醒反応が引き起こされる恐れがあります。また、いびきの原因となる気道の狭窄により、胸腔内の圧力が上昇すると、それによる機械的刺激が覚醒反応を引き起こす恐れもあります。これらの要因により、いびきの激しい方が昼間の過眠を引き起こしやすいという仮説が立てられています。
睡眠時無呼吸症候群は放置しても問題ないですか?
睡眠時無呼吸症候群には、日中の眠気やだるさなど、自覚しにくい症状もありますが、ここ数年の研究によると、高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクが、一般の方よりも数倍も高いことが分かっています。
高血圧や糖尿病の怖さは、ほとんど自覚症状がないことです。気付いた時にはかなり進行してしまい、動脈硬化などの血管障害が引き起こされ、脳出血や脳梗塞、心筋梗塞などの重篤な状況に至る可能性もあります。
昼間になると強い眠気に襲われる場合や、いびきを指摘された場合は、お早めにご相談ください。