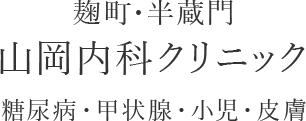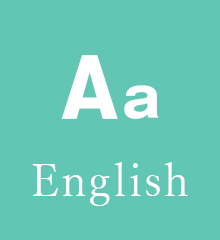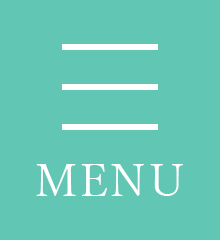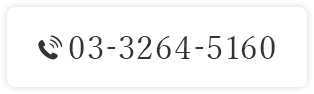高血圧について
 血圧は、1日の中でも睡眠、食事、日常的な活動、精神的緊張などによって上がったり下がったりします。また、計測した環境(自宅か医療機関か)によっても、測定値が異なることがあります。身体的にも精神的にもリラックスした状態で血圧を測定し、その数値が基準より高い場合、高血圧とみなされます。
血圧は、1日の中でも睡眠、食事、日常的な活動、精神的緊張などによって上がったり下がったりします。また、計測した環境(自宅か医療機関か)によっても、測定値が異なることがあります。身体的にも精神的にもリラックスした状態で血圧を測定し、その数値が基準より高い場合、高血圧とみなされます。
高血圧が続くと、血管への負担が大きくなり、動脈硬化が進み、脳卒中や心臓病など重篤な疾患を発症するリスクが高まります。高血圧の状態を放置せずに医師の指示に従い、適切な治療を受けて血圧を管理することが重要です。
血圧とは何か
心臓が力強く収縮して血液を体中に送り出す際、動脈内の血液が血管壁にかかる圧力が「血圧」として表れます。血圧は収縮期に高くなり、拡張期には低くなります。
朝起きた時には高く始まり、徐々に上昇し、昼間にピークを迎えます。そして、夕方に向かってゆっくりと下がり、就寝時には最も低いレベルになります。このように、血圧は1日の中で様々な変化を見せますし、気温の変化や食事、運動、ストレスなどによる影響も受けます。
血圧は、次の4つの要素によって数値が決まります。血圧の数値はmmHgで表されます。
- 心臓が1回の収縮で送り出す血液量(心拍出量)
- 血管の柔軟性
- 末梢血管に血液が流れる際の抵抗力(血管抵抗)
- 血液の粘性
診療室血圧と家庭血圧
 血圧は時間や環境によって変動します。医療機関で測る血圧は「診察室血圧」と呼ばれ、移動中の活動や医師の前での緊張によって、通常より高くなる傾向があります。一方、自宅で測る血圧は「家庭血圧」と呼ばれ、医療機関で測る時よりもリラックスした状態で計測できるため、通常は低めになります。
血圧は時間や環境によって変動します。医療機関で測る血圧は「診察室血圧」と呼ばれ、移動中の活動や医師の前での緊張によって、通常より高くなる傾向があります。一方、自宅で測る血圧は「家庭血圧」と呼ばれ、医療機関で測る時よりもリラックスした状態で計測できるため、通常は低めになります。
現在では、診察室血圧はあくまで目安として、朝起きた時と夜寝る前に、1日2回定期的に計測し、変化を確認することが重要視されています。また、精密な検査が必要になった場合、特別な装置を24時間装着して計測する「24時間血圧モニタリング検査」が実施されることもあります。
高血圧の症状
 高血圧特有の症状はありません。進行すると頭痛、めまい、肩こり、息切れなどが現れる可能性があります。しかし、これらの症状は高血圧以外の原因でも現れることがありますので、これらの症状だけで高血圧を疑うのは難しいです。
高血圧特有の症状はありません。進行すると頭痛、めまい、肩こり、息切れなどが現れる可能性があります。しかし、これらの症状は高血圧以外の原因でも現れることがありますので、これらの症状だけで高血圧を疑うのは難しいです。
血圧異常を指摘されたら、すぐに医師に相談し、進行を防ぐために血圧を管理することが重要です。
高血圧の原因
① 本態性高血圧症
(一次性高血圧)
原因がはっきりとしていない高血圧で、患者様の約90%がこの本質的高血圧症に該当します。生活習慣病や遺伝、加齢などが影響していると考えられており、具体的な原因として、以下の要素が挙げられます。
- 塩分の過剰摂取
- 運動不足
- ストレス
- 肥満
- 喫煙
- 過労
- 睡眠不足
- 遺伝
② 二次性高血圧症
特定の疾患が原因となる高血圧です。原因疾患の治療を優先し、血圧を下げていくことが重要です。主な原因として、以下が挙げられます。
腎実質性高血圧
腎機能の低下により、体内に塩分が蓄積され、血圧が上昇します。
腎血管性高血圧
動脈硬化によって腎動脈が狭くなり、血圧が上昇します。
原発性アルドステロン症
腎臓の上にある副腎から分泌されるアルドステロンというホルモンを増やす良性腫瘍が、血圧の上昇の原因となります。
クッシング症候群
副腎から分泌されるコルチゾールホルモンを増やす良性腫瘍によって、血圧が上昇します。
褐色細胞腫
副腎で分泌されるカテコラミンホルモンは、血圧を上げる作用があります。このホルモンが増加することで、血圧が上昇します。
薬剤性高血圧
薬物治療によって血圧が上昇します。
※その他、甲状腺ホルモンや副甲状腺ホルモンの異常、睡眠時無呼吸症候群などにより高血圧を起こすことがあります。
高血圧の治療
 最初に、食事や運動などの日常生活を見直します。それでも数値に変化がない場合は、高血圧治療薬の使用を検討します。二次性高血圧症の場合は、まず原因となる病気の治療を優先します。
最初に、食事や運動などの日常生活を見直します。それでも数値に変化がない場合は、高血圧治療薬の使用を検討します。二次性高血圧症の場合は、まず原因となる病気の治療を優先します。
難治性高血圧症は近年増加しており、複数の高血圧治療薬を服用しても改善が見られないことがあります。この場合、二次性高血圧症の可能性が考えられるため、気になる方・心当たりのある方は、お気軽に当院までご相談ください。
生活習慣の改善
塩分制限
塩分を多く摂取すると、血中の塩分濃度が上昇します。喉が乾くと、水分を多く摂取して血液の塩分濃度を薄め、体内水分を増やそうとします。これにより、血液量が増えて血圧が上昇します。
日本高血圧学会によると、高血圧の予防・治療のための塩分摂取目安量は、1日に6g未満とされています。塩分を抑えることは、血圧の管理において非常に重要です。1日に摂取する食材自体に含まれる塩分は既に3gですので、調味料からの摂取量は3g未満にする必要があります。インスタント食品や加工食品、漬物、干物などは塩分が多く、1日の摂取量を超える可能性があるため、素材の味を引き立てる調理法を心がけると良いでしょう。そのため、出汁や薬味、ハーブ、スパイス、レモンなど、塩分以外の香り付けを取り入れて、食事を楽しむことを推奨しています。
体重制限
高血圧を予防・改善するためには、体重をチェックして肥満を防ぐことが非常に有効です。標準体重を知るために、以下の計算式を使って目安を把握することが重要です。
標準体重(Kg)=身長(m)×身長(m)×22
肥満や運動不足は、高血圧のリスクを高めます。食事のコントロールや適度な運動習慣は、高血圧予防に不可欠です。さらに、運動には全身の血液循環を促進する効果があります。運動不足に陥ると、血液循環が悪化し、血圧が上昇しやすくなります。
運動
適度な運動を継続的に行うことによって、血流が促進され、血行が改善されます。それにより、筋力や骨の強度が向上し、体重をコントロールできるようになります。また、ストレスを軽減するだけでなく、呼吸機能も改善されます。汗をかく運動は非常に健康に良いので、定期的に行うと、高血圧改善に期待できます。
運動の内容・強度・頻度などは、医師と相談してから決めることが望ましいです。特に、心臓疾患や膝、腰の問題、高血圧の程度に応じては、医師の指示に従った方が良いとされています。
飲酒
過度のアルコール摂取は高血圧を引き起こすリスクがあります。1日の適正アルコール摂取量は25gです。
ビールの場合は500ml、日本酒なら180mlまでが適量です。前日に飲酒していない場合でも、量を増やしたりしないように、1日の適切な量をきちんと守りましょう。
禁煙
喫煙をしていると、タバコの成分が血管を収縮させてしまうため、高血圧を引き起こし、動脈硬化などのリスクを上昇させます。そのため、高血圧治療を進める際には、喫煙習慣を止めることが重要です。また、喫煙は高血圧に加えて、呼吸器疾患や歯周病など、全身の健康に影響を与えることが知られています。喫煙する習慣がある方には、禁煙をお勧めしております。
高血圧の予防
血管の健康を守るために、血圧を正常範囲に保つことは非常に重要です。
医師と十分に相談しながら、以下のポイントに気を付けて、高血圧を予防しましょう。
- 塩分の摂取を控えるよう心がけましょう(1日の食塩摂取量の目安は6.0g未満)。
- 野菜と果物は積極的に摂取しましょう(腎障害のある方は医師へご相談ください)。
- 体重を管理することを意識しましょう(BMIを25.0以下にすることを目指す)。
- 適切な有酸素運動(例:ウォーキングなど)を週に最低3回続けましょう。
- 飲酒は程々にしましょう(ビールなら1日500mL、日本酒なら1日1合が目安)。
- 禁煙を心がけましょう。
- ストレスを溜め込まないようにし、心と体をリラックスさせましょう。