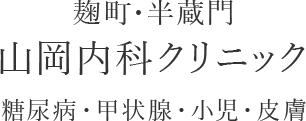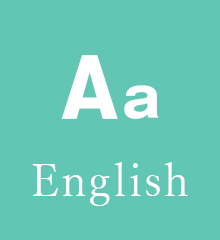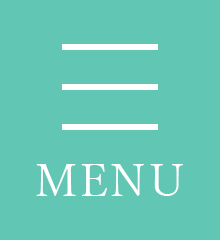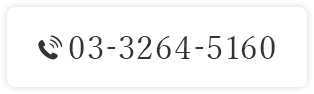- 小児科について
- 子どものよくある症状
- 子どものよくある疾患
- 代表的な症状・疾患
- 乳幼児健診について
- 千代田区の乳幼児健診
- 乳幼児健診の流れ
- 当院で可能な健診の検査内容
- お子様の成長と
発達スピードが心配な方へ
小児科について
 当院で治療が行える病気としては、急性の症状(発熱や咳、鼻水、腹痛、下痢、嘔吐、発疹など)、慢性の病気(アトピー性皮膚炎、気管支喘息、花粉症などのアレルギー性疾患)、慢性的な症状(長引く咳、便秘、下痢、頭痛、何度もできる湿疹など)、耳・鼻・皮膚に関する問題など、広範囲にわたります。
当院で治療が行える病気としては、急性の症状(発熱や咳、鼻水、腹痛、下痢、嘔吐、発疹など)、慢性の病気(アトピー性皮膚炎、気管支喘息、花粉症などのアレルギー性疾患)、慢性的な症状(長引く咳、便秘、下痢、頭痛、何度もできる湿疹など)、耳・鼻・皮膚に関する問題など、広範囲にわたります。
また、育児に関するご相談や授乳、食事、成長・発達、予防接種のスケジュールなどについても、女性の小児科専門医が適切にアドバイスいたします。
当院で診察を受けた結果、専門的なケアが必要になった場合には、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、外科などの専門医・提携医療機関へのご紹介も行っています。このように、適切な治療を受けられるよう、「地域の子どものかかりつけ医」を目指し、診療の他にも、子育てを全般的にサポートしています。どんな些細なお悩みでもお気軽にご相談ください。
子どものよくある症状
- 咳
- 発熱を繰り返す
- 頭痛
- 鼻水
- 喉が痛む
- 腹痛
- 下痢
- 嘔吐
- ひきつけ(痙攣)
- 発疹
- 湿疹が繰り返し出る
- 顔色が良くない
- 食欲が湧かない
- 元気がなさそうに見える
- 肌が赤い
- 息苦しそう
など
子どものよくある疾患
- 咳
- 発熱
- 腹痛
- 便秘
- 下痢
- 痙攣
- 血便
- 肺炎(マイコプラズマ肺炎など)
- アトピー性皮膚炎
- 食物アレルギー
- 喘息
など
代表的な症状・疾患
発熱
 体温が37.5℃以上あると、発熱とされます。お子様の場合、着るものや布団の枚数が多すぎたり、暖房の影響、外の気温が体温による影響を受けたりしている可能性があるため、お気をつけください。体は少し薄着にしてから、しばらく時間をおいて何度か測ることで、正確な体温を測定できます。
体温が37.5℃以上あると、発熱とされます。お子様の場合、着るものや布団の枚数が多すぎたり、暖房の影響、外の気温が体温による影響を受けたりしている可能性があるため、お気をつけください。体は少し薄着にしてから、しばらく時間をおいて何度か測ることで、正確な体温を測定できます。
生後3カ月未満の赤ちゃんが発熱した場合、重症細菌感染症などの可能性があるため、必ず小児科へお越しください。
また、生後3カ月以上のお子様で、食欲があって元気な様子を見せている場合は、あまり過度に心配しなくても問題ありません。けいれんや意識の混濁がある場合はもちろんですが、水分をきちんと摂っているか、尿の量が減っていないか、ぐったりしていないかなどの様子をチェックし、何か異常が見られた場合は、すぐにご相談ください。
腹痛
便秘や胃腸炎により、胃の不快感が発生するケースがほとんどです。しかし、中には、虫垂炎などの外科的疾患や、喘息や肺炎といった呼吸器疾患、食物アレルギー、膀胱や腎臓などの疾患によって腹痛が生じている可能性もあります。すぐに治療しなければならないケースもありますので、放置は禁物です。
子どもは、自分の体調不良を「お腹が痛い」と訴えることもありますので、子どもが低年齢の場合は、全身の状態を細かく観察しましょう。
嘔吐
子どもは非常に嘔吐しやすいです。強い咳き込みや激しく泣くことで嘔吐することも少なくありません。嘔吐した後でも、体調に問題がなさそうであれば、すぐに受診する必要はありません。しかし、その状態でも、症状がないか観察するよう意識してください。
嘔吐を繰り返している、水分がとれていない、もしくは意識が悪い場合には、迷わずに受診してください。
また乳児で嘔吐を繰り返している場合は、腸管の一部が後ろの腸管にはまり込み、腸が閉塞してしまう腸重積の可能性が疑われます。腸重積は、迅速な診断・治療が必要ですので、嘔吐に加えて不機嫌な状態や血便などを伴う場合でも、すぐに受診してください。
下痢
乳児は下痢をしやすい傾向がありますが、ミルクや母乳を通常通りに摂取し、機嫌も良好であれば、いったん経過観察しても問題ありません。しかしながら、元気がなかったり、水分摂取が不十分だったり、尿量が減少している場合には、脱水症状の兆候が見られる可能性があります。乳児は脱水症状が深刻化しやすいため、口内や唇の乾燥、泣いても涙が出ない、尿の色が濃い、尿の量が減少している場合は、迅速に医師の診察を受けてください。
泣き方がいつもと違う
泣くことは、赤ちゃんが自分の気持ちを伝える方法の1つです。「泣き方がいつもと違う」と感じた場合は、まず体温を計り、そこから様子を見守ってください。また、急に泣くことを止め、元気がなくなるような様子を見せた場合には、早急に治療を受ける必要があるかもしれません。
呼吸しにくい・息苦しい
肺炎や喘息などにより、息苦しいと訴えることがあります。言葉で苦しさを表現できない年齢のお子様ですと、通常よりも呼吸回数が多くなるか、肩で呼吸しているか、肋骨の下がペコペコするような呼吸をしているか、横になると苦しくて睡眠をとれず、夜中に何度も目が覚めるかなど、そのような状態になっていないかを観察しましょう。
また、急な咳き込みとともに息苦しさが始まる場合は、誤って異物を吸い込んでしまい、気管に詰まってしまう可能性もあるため、迷わずに受診しましょう。
アレルギー
人間は、様々な病原体や異物から身を守るための免疫反応を持っています。しかし、この免疫反応が特定の異物(花粉やハウスダスト、食品など)に対して過敏に反応すると、アレルギーと呼ばれる不都合な症状が現れます。代表的なアレルギー疾患には、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、気管支喘息、アレルギー性鼻炎・花粉症などがあります。当院では経験豊富な専門医が、子どものアレルギー疾患に丁寧に対応しております。アレルギー疾患の発症には、遺伝的な体質も大きな影響を及ぼします。何らかのアレルギー疾患が疑われる場合だけでなく、ご両親や兄弟にアレルギー疾患の方がいる場合にも、早期治療により予防できたり、有効な治療を行えたりする可能性もあるため、一度ご相談くださいま。
夜尿症
「子どものおねしょ」とは、5歳以上の子どもが月に1回以上の頻度で、かつ3カ月以上に渡って、夜間就寝中に尿失禁をしてしまう状態です。膀胱の機能が成長しきっていないことが原因であり、自然に改善されることが一般的です。しかし、治る時期は個人によって異なります。
長期間続くおねしょは、親子ともに精神的な負担となることが多いため、子どもがコンプレックスを抱えるのを防ぐためにも、就学前には一度医師に相談することをお勧めします。また、日中にも尿失禁が見られる場合は、別の病期が隠れているかもしれませんので、早急に医療機関へご相談ください。
尿路感染症
尿路(腎臓・尿管・膀胱・尿道)内で、ウイルスまたは細菌による感染が起こり、それによる炎症によって生じる疾患です。乳幼児期には男児の発症率が高く、成長するにつれて女児の罹患率が上昇する傾向が見られます。
典型的な症状には、頻尿、排尿時の痛み、発熱、下腹部の不快感、腰や背中の痛みなどがありますが、幼い子どもですと嘔吐や発熱だけが現れるケースも珍しくありません。
咳や鼻水・腹痛・下痢などを伴っていない、原因不明の持続的な発熱が続く場合は、尿路感染症の可能性も疑われますので、警戒が必要です。尿路感染症が何度も起こっている場合には、先天的な腎臓・尿路の形態異常がないか、調べる必要があります。
血尿・蛋白尿
血尿や蛋白尿に関しては、自覚症状よりも保育園・幼稚園・学校での尿検査で異常が見つかるケースがほとんどです。生理的な原因による場合は特に心配しなくても問題ありません。しかし、腎臓疾患や全身性の疾患による可能性もあるため、必ず医師の診察を受けるようにしてください。
咳・喘息
小児科へ受診する子どもの中でも、最も見られる症状は「咳」です。これは通常、風邪ウイルス感染による「風邪症候群」によるものです。
発熱を伴っていない、かつ食欲があって普段通り元気な場合は、あまり心配しなくても問題ありません。
咳と一口に言っても、乾いた咳、粘液の絡んだ咳、オットセイのような鳴き声のような咳など、多岐にわたります。オットセイのような咳は、「犬吠様咳嗽(けんばいようがいそう)」とも呼ばれ、クループ症候群や急性喉頭蓋炎など、声帯周辺の炎症によって引き起こされる症状でもあります。
喘息の症状として咳が見られることもありますが、子どもでは風邪と喘息を区別するのは難しい場合も多いと言われています。
通常よりも呼吸回数が多い、肩呼吸している、肋骨の下がペコペコするような呼吸方法をしている、横になると苦しくて夜中に何度も目が覚める、などの症状に気づいた場合は、よく観察し、異常を感じたら受診してください。
鼻水・鼻づまり
多くの場合、
- 透明でサラサラの鼻水(風邪のひき始めやアレルギーによるもの)
- 白い鼻水(ピークを迎えた時期の風邪に見られるもの)
- 粘り気があり、黄色または緑色の鼻水(風邪や副鼻腔炎(蓄膿症)に由来するもの)
などといった傾向がありますと、鼻水の性状だけで簡単に見分けることは難しいと言われています。もし鼻水が長引くようでしたら、一度当院までご相談ください。
乳児の場合、鼻水や鼻づまりにより、母乳やミルクを上手に摂取できなくなる可能性があることや、寝つきが悪くなることもあります。3〜4歳までは、自分で鼻をかむことができないため、自宅で適宜鼻吸引をしてあげると良いでしょう。3〜4歳になれば、自分で鼻をかむ練習を少しずつ始めることもお勧めです。
また、アレルギー性鼻炎などによる慢性的な鼻水や鼻づまりがあると、睡眠の質が悪化し、集中力の低下や昼間の眠気、イライラしやすくなるなどの悪影響を及ぼすことがあります。そのため軽視せずに、しっかりと診断を受けて適切な治療を行うことが重要です。
当院には鼻吸引器(いわゆる鼻吸い器)がありますので、ご希望の方はご来院ください。(鼻吸いのみの目的でのご来院も可能です。)
乳幼児健診について
乳幼児健診の目的
赤ちゃんの発育速度は非常に早く、乳幼児健診では継続的に健康状態を確認することが重要です。栄養状態、成長や発達の状況、先天性疾患の有無などをチェックし、異常が発見された場合には、迅速に適切な医療を提供します。
また、予防接種の状況や将来の予定についてもお伺いします。保護者の方が気になることや心配ごとを相談できる機会でもあるため、何かお困りのことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
千代田区の乳幼児健診
乳幼児健診は、母子保健法により規定された公的な健診です。
千代田区では、3~4か月児健康診査、6~7か月児健康診査、9~10か月児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査、5歳児健康診査が実施されています。
当院では、これらの乳幼児健診だけでなく、他の年齢層の健診も希望に応じて行っています。
「3~4か月児健診」「1歳半健診」「3歳児健診」「5歳児健診」は千代田保健所で実施しており、生年月日で受診日が決められています。
詳しい日程は千代田区のお子さんの健康と相談ページをご確認ください。
乳幼児健診の流れ
1ご予約
当院で行われる乳幼児の健康診断は、ご予約が必要となりますので、事前にWEBまたはお電話でのご予約をお願いいたします。
持ち物
- 母子手帳
- 自治体から配布された受診票(ご自宅で記入後、お持ちください)
- 保険証、医療証
- 着替え、おむつなど
当日は、脱ぎ着しやすい服装でご来院くださいませ。
2健診当日
身体計測の時間を確保するため、まずは予約時間の10分前にご来院いただきます。
3問診・身体計測
問診を行い、赤ちゃんの身長、体重、頭囲、胸囲を計測します。
4診察
医師による診察では、成長や発達状況、異常の有無などをチェックします。
5育児相談
育児に関する相談も受け付けております。生活習慣のアドバイスやスキンケア、離乳食に関する相談など、どんなことでもお気軽にお聞きください。
6終了
健診が終わりましたら、受付で保険証・受診票・母子手帳を返却後、お帰りいただけます。受付時には、次回の健診や予防接種の予約も可能ですので、お気軽にご相談ください。
当院で実施可能な
健康診断の検査内容
- 一般的な内科診察
- 身体計測(身長や体重・頭囲など)
- レントゲン
- 心電図検査
- 尿検査
- 血液型検査
- 視力・色覚検査
- 聴力検査
- ツベルクリン反応(結核検査)
下記の検査は取り扱っておりません
- スポットビジョンスクリーナー(近視・遠視・乱視・斜視の簡易スクリーニング)
- 発達検査や知能検査
お子様の成長と発達スピードが心配な方へ
 成長とは、子どもの体の大きさが変わることを指し、発達とは能力が変化することです。
成長とは、子どもの体の大きさが変わることを指し、発達とは能力が変化することです。
乳幼児の成長と発達には、同じ月齢の子どもでも、在胎週数や出生時の身長・体重、生活環境、性別によって個人差が大きくあります。
母子手帳に載っている情報や成長グラフは参考程度に留めていただき、必ずしもその通りに成長したり発達したりするわけではありません。お子様にとって適切な成長と発達のペースが尊重されることが重要ですので、不安を感じる場合はお気軽にご相談ください。
もし成長や発達に問題がある場合、医師による適切な対応が必要と判断された時には、連携医療機関をご紹介したり、定期的なフォローアップ診察を行ったりしますので、安心してください。