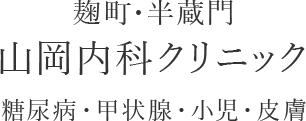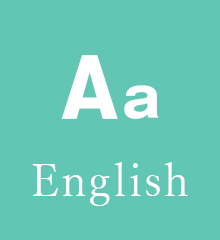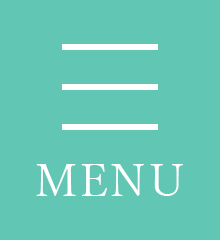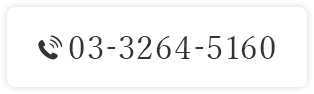骨粗鬆症とは
 古くなった骨の成分は破骨細胞によって徐々に破壊され、体外に放出されます。一方で、骨芽細胞により新しい骨の成分が生成されると、破壊された分が補填され、一貫して新陳代謝を続けながら、一定の硬度を保ち続けています。
古くなった骨の成分は破骨細胞によって徐々に破壊され、体外に放出されます。一方で、骨芽細胞により新しい骨の成分が生成されると、破壊された分が補填され、一貫して新陳代謝を続けながら、一定の硬度を保ち続けています。
この骨の新陳代謝システムに障害が生じると、破骨細胞が過剰に活動したり、骨芽細胞が正常に機能しなくなったりすると、古い骨の成分だけが連続的に排出され、骨の密度が減って脆弱な状態になります。これが骨粗鬆症です。骨粗鬆症は、加齢や喫煙、過度な飲酒などによって引き起こされる可能性がありますが、特に閉経に伴う女性ホルモンの変化が大きく関与しています。
骨粗鬆症を発症すると、些細な衝撃でも骨折してしまう可能性があるため、定期的な骨密度検査と早期治療が大切です。
骨粗鬆症の原因
主な要因は加齢による骨の減少です。しかし、ホルモンバランスの変化、生活習慣の影響(例:食事や運動)、医薬品なども大きな影響を与えます。骨はカルシウムが蓄積される「骨形成」とカルシウムが放出される「骨吸収」という代謝プロセスによって保たれているため、これらの機能に障害が生じると、骨粗鬆症が発症・進行するリスクが高まります。
加齢による骨量の減少
骨量は男女ともに20代前半がピークとされ、一定の骨量を保つことができるのは40代半ばまでです。その後には、年々骨量が減少し続け、骨は加齢とともに老化していきます。
更年期・閉経
女性は閉経により、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が急激に低下します。エストロゲンは骨形成を促進し、骨吸収を抑える働きを持っているため、閉経後の女性は骨粗鬆症のリスクが上昇します。
エストロゲンの分泌量が不安定に低下し始める更年期に入ったら、骨粗鬆症に警戒が必要です。
カルシウムの調整機能の衰え
骨の形成・吸収などのコントロール機能を調整している副甲状腺ホルモンをはじめ、ビタミンDやカルシトニン、エストロゲンなどに異常が生じると、骨粗鬆症を含む骨の問題を引き起こしやすくなります。
カルシウム・ビタミンD・
ビタミンKの摂取不足
骨形成には、カルシウム・ビタミンD・ビタミンKが必須です。これらの栄養素が不足すると骨が脆くなる恐れがあります。
運動
適度な負荷がかかると骨が強化されます。そのため、運動不足は骨の強度を低下させます。さらに、運動不足により筋力やバランス調整機能が低下し、転倒リスクが高まり、骨折の危険性が増すことがあります。
嗜好品(飲酒・喫煙)
喫煙はカルシウムの吸収を妨げ、骨密度を減少させる要因にもなります。また、過度の飲酒も骨粗鬆症を進行させるリスクがあります。
病気や薬剤の影響
関節リウマチ、糖尿病、慢性腎臓病(CKD)などの疾患や、長期間にわたるステロイドの使用は、骨が脆くなるリスクを高めます。これらの病気や薬によって引き起こされるものは「続発性骨粗鬆症」と称されています。
骨粗鬆症の検査
「骨粗鬆症による圧迫骨折が起こっていても、痛みがほとんどない」という症例は珍しくありません。また、慢性的な腰痛や背中の痛みが、実は骨折によって引き起こされている場合もあります。このように自覚症状が現れにくい骨粗鬆症をすぐに発見するために、検査が必要とされます。
特に女性の方々は、骨量が減少し始める40歳頃から定期的に検査を受けることをお勧めします。また、40歳未満の若い方々も、早めに検査を受けることで、骨粗鬆症の早期発見だけでなく、予防のための骨の健康管理に役立てることができます。
骨粗鬆症の検査方法は2つあり、「画像検査による骨量(骨密度)測定」、そして「血液や尿による検体検査」があります。
画像検査
 一般的なX線検査法として、DXA(デキサ)法、MD法、超音波検査が挙げられます。MD法はX線を使用し、手の骨と厚さが異なるアルミニウム板を同時に撮影し、骨とアルミニウムの密度を比較して測定する検査です。超音波検査は踵や脛の骨に超音波を使用して測定する方法です。必要に応じて適切な医療機関へご紹介させていただきます。
一般的なX線検査法として、DXA(デキサ)法、MD法、超音波検査が挙げられます。MD法はX線を使用し、手の骨と厚さが異なるアルミニウム板を同時に撮影し、骨とアルミニウムの密度を比較して測定する検査です。超音波検査は踵や脛の骨に超音波を使用して測定する方法です。必要に応じて適切な医療機関へご紹介させていただきます。
血液検査・尿検査
血液検査や尿検査により骨代謝マーカーを行うことで、骨の新陳代謝速度が明らかになります。骨吸収を示す骨代謝マーカーが高い方は骨密度の低下速度が速いため、骨密度値に関係なく、骨折のリスクが高いと見なされます。
骨粗鬆症の治療について
食事療法
 骨の基本成分はカルシウムやたんぱく質です。加えて、「骨のリモデリング」と呼ばれる仕組みでは、破骨細胞が古い骨の成分を取り込み、骨芽細胞が新しい成分を提供します。このプロセスには、ビタミンDやビタミンKなどが必要です。これらの栄養素を含む食品を積極的に摂取し、バランスの取れた食事が重要です。
骨の基本成分はカルシウムやたんぱく質です。加えて、「骨のリモデリング」と呼ばれる仕組みでは、破骨細胞が古い骨の成分を取り込み、骨芽細胞が新しい成分を提供します。このプロセスには、ビタミンDやビタミンKなどが必要です。これらの栄養素を含む食品を積極的に摂取し、バランスの取れた食事が重要です。
アルコールやカフェインの過剰摂取は、カルシウムを尿と一緒に排出しやすくする恐れがあります。また、リンは血中でカルシウムとのバランスを取ろうとする性質を持っているため、過剰摂取をしてしまうと、骨からカルシウムを奪う傾向があります。そのため、過剰摂取は避けるようにしましょう。
運動療法
骨は、体重による負担が増えれば増えるほど、自ら強化しようとする性質があります。また、筋肉は関節や骨を支え、全体のバランスを改善します。筋肉が強化されると、転倒のリスクも軽減されるため、運動習慣は非常に重要です。
なお、激しすぎる運動はかえって故障の原因となることがあるので、注意が必要です。適度な有酸素運動、特にウォーキングは、特別な機器や環境がなくても実践できるためお勧めです。初めは1日30分程度から始めて、習慣化してみましょう。毎日行うのが難しい場合には、週に3回程度から始めるだけでも問題ありません。