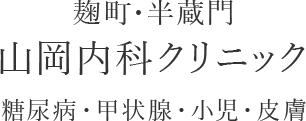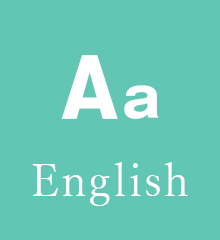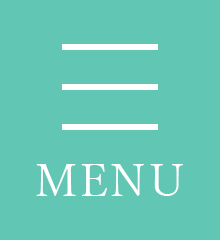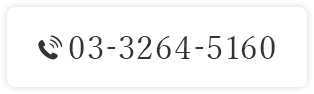内科
内科とは
 内科は発熱、咳、腹痛、下痢、胸痛、動悸、息切れなど、急な体の不調について相談するきっかけにもなる、重要な診療科目です。
内科は発熱、咳、腹痛、下痢、胸痛、動悸、息切れなど、急な体の不調について相談するきっかけにもなる、重要な診療科目です。
当院では、日本内科学会が認定する内科医の資格を有している院長が、豊富な知識を活かして様々な不調の原因を正確に診断し、適切な治療や生活指導を行っております。どんな症状にお悩みでも、お気軽にご相談ください。
原因が特定できない体調不良にも対応
風邪やお腹の調子が悪いわけでもないのになんとなく調子が悪いなど、原因が分からない体調不良が起こることもあります。当院では、このような症状に真摯に向き合い、原因を探り、適切な治療を提供しています。地域の皆さまが気軽に相談できるかかりつけ医としてお手伝いさせていただいております。
内科でよく見られる症状
- 体調が優れず、熱を計ったら38℃以上の高熱がある
- 長く微熱が続き、治まらない
- 喉がイガイガと違和感が続く
- 咳がひどくなりだした
- 足や手の浮腫みが気になる
- 呼吸が苦しくて歩きにくい
- 突然疲れやすくなってきた
- 体がずっとだるい
- ダイエットしていないのに体重が減っている
- 吐き気や嘔吐がある
- 食欲がなく、食事量が減っている
など
内科で扱う主な病気
風邪症候群
 風邪は、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、喉の痛み、咳など、鼻から喉にかけての上気道に急性炎症を引き起こす疾患の総称です。医学的には「風邪症候群」と呼ばれ、発熱、倦怠感、頭痛、食欲不振などの全身症状が現れることもあります。
風邪は、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、喉の痛み、咳など、鼻から喉にかけての上気道に急性炎症を引き起こす疾患の総称です。医学的には「風邪症候群」と呼ばれ、発熱、倦怠感、頭痛、食欲不振などの全身症状が現れることもあります。
風邪は、主に粘膜への感染が原因であり、およそ80~90%がウイルスによるものです。風邪は病気の元とも言われており、適切に治さないと、気管支炎などに繋がる恐れもあります。
インフルエンザ
インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染して発症する感染症です。何種類もの型がありますが、A・B・Cの3種類というヒトに感染するウイルスのうち、毎年異なる型が感染します。流行は11月頃から始まり、ピークを迎えるのは1月で、3月くらいまで続きます。
インフルエンザは、風邪のような咳、鼻水、喉の痛みという風邪症状に加えて、38℃以上の高熱、頭痛、倦怠感、筋肉や関節の痛みなどの全身症状が現れる傾向があります。感染後の潜伏期間は1~3日ほどで、通常1週間ほど症状が持続し、次第に改善していきます。
感染力が強く、稀に爆発的に感染を広げることがあるため、症状が出たらできるだけ早く受診することをお勧めします。
喘息
喘息は、空気が通過する気管支が炎症を繰り返すことによって過敏になる状態を指します。この過敏さによって、些細な刺激でも気道が狭まり、激しい咳や呼吸困難、ヒューヒュー・ゼイゼイといった喘鳴など特徴的な症状が現れます。これを喘息発作と呼びます。
喘息は主に小児に見られる疾患であり、その多くはアレルギーが原因とされています。
一方、成人の場合には、アレルギーだけでなく、過労や化学的刺激、ストレスなどの心因的要素、気候などの環境的要因も原因とされます。
まずは原因を特定して、発作を予防することが重要です。
生活習慣病
厚生労働省からは「食習慣・運動の習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」と定義されている疾患です。具体的には高血圧症、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、肥満症などがこれに含まれますが、これらの疾患はほとんど自覚症状がなく、気付いた時には動脈硬化などを起こし、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血などの重篤な合併症を発症する危険性があります。多くの生活習慣病は、定期的な健康診断で早期発見が可能です。毎年1度の受診を心掛け、異常が見つかれば速やかに相談してください。
糖尿病
糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンにより、ブドウ糖を調節する役割が上手く果たせなくなったり利用できなくなったりした結果、血中にブドウ糖が過剰に溜まる疾患です。
1型と2型があり、1型はインスリン産生量に問題があるタイプ、2型はインスリンの量が不十分だったりスムーズに機能しなくなったりするタイプとされています。そして、妊娠時の体の機能により、一時的に発症してしまう妊娠糖尿病や、特定の疾患や機能によるものなど様々な原因があります。そのうち2型糖尿病が多く、偏食や食習慣の乱れ、運動不足などが原因で発症するケースが多いため、生活習慣病に分類されています。
糖尿病は様々な合併症を引き起こすため、「合併症のデパート」とも呼ばれており、命に関わるものや失明を招くものもあります。早期の段階に発見し生活習慣を適切に管理していくことが重要です。
高血圧
血圧とは、心臓が血液を全身に送り出す際の血管壁にかかる力を指し、心臓が収縮して血液を送り出す際には上昇します(収縮期血圧=上)。一方、心臓の拡張により、静脈から血液を受け取る際には低下します(拡張期血圧=下)。典型的には、医療機関の診察室で測定した場合、上の血圧が140mm/Hg以上、下の血圧が90mm/Hg以上の場合が高血圧とみなされます。
血圧が高くなると、血管壁に掛かる負担が増大し、動脈硬化などの血管疾患の発症リスクが高まり、最悪の場合、脳卒中や心筋梗塞の発症リスクが増加します。肥満、塩分摂取過多、運動不足などの生活習慣に起因することが一般的なため、生活習慣を見直し、血圧を適正範囲にコントロールすることが極めて重要です。それでも血圧が目標範囲に達しない場合、薬物療法が必要となります。
脂質異常症(高脂血症・高コレステロール血症)
脂質は人体にとって必要不可欠な栄養素です。しかし、血液中に脂質が多すぎたり少なすぎたりすると、体調に異常が起こります。このような状態を脂質異常症と呼びます。
脂質は血液中で主にコレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)として流れています。コレステロールには、細胞に脂質を運ぶLDLコレステロールと、余分な脂質を回収するHDLコレステロールがあります。これらの成分が適切なバランスで作用することが重要です。LDLコレステロールや中性脂肪が過剰になったり、HDLコレステロールが不足したりすると、血液がドロドロになり、動脈硬化や動脈瘤などの原因となる可能性があります。
これらのバランスは生活習慣の乱れによって引き起こされやすいですが、遺伝的要因も影響しているとされています。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠中に呼吸が停止する、もしくは呼吸が弱まる、いびきをかくなどの状態が見られた場合、睡眠時無呼吸症候群の可能性が考えられます。
睡眠の質が低下すると、日中の生活にも悪影響を及ぼします。また、血管や心臓への負担も大きくなり、最悪の場合、突然の死に繋がる恐れもあります。さらに、睡眠時無呼吸症候群が高血圧や糖尿病などのリスクを引き上げることも分かっています。
睡眠時の問題であり、自覚しにくい疾患ですが、周りの方からいびきの指摘がある、熟睡感がない、睡眠時間を確保しているのにもかかわらず日中や食後の眠気が強いなど、何らかの兆候があれば、お早めにご相談ください。
アレルギー性鼻炎
アレルギー性鼻炎は、何らかのアレルギーによって鼻粘膜に炎症が生じ、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状が持続する病態です。原因は、スギやヒノキなどの花粉による季節性アレルギーや、ハウスダスト(ダニなど)や薬剤などによる通年性アレルギーなどが挙げられます。原因物質を見つけ出し、適切な治療を行えば症状を軽減させることは可能です。
花粉症
花粉症は季節性アレルギーの代表的な症状です。春にはスギやヒノキ、初夏から夏にかけてのシラカンバやイネ科の花粉、秋にはブタクサやヨモギなど、ほぼ1年を通じてアレルゲンとなる花粉が舞います。主な症状としては、鼻づまりや鼻水、くしゃみ、目のかゆみ、目の充血、咳、湿疹、肌荒れなどが挙げられます。
発熱・風邪症状外来
発熱・風邪症状外来とは
発熱・風邪症状外来は、発熱や咳、鼻水、喉の痛みなどの風邪症状がある患者様を対象に、診療を行っている診療科です。新型コロナウイルス感染症だけでなく、他の病気による症状も診断・治療する診療科目となっております。
発熱は、通常、健康な体に異常がある場合に発生します。
当外来では、発熱や風邪症状が新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ、または他の原因(膠原病など)から引き起こされたものかを見極め、適切な治療を行っております。
このような症状は発熱・風邪症状外来を受診しましょう
- 37.5℃の微熱から38℃以上の高熱がある
- 冷や汗が出る
- 寒気がする
- 喉が痛い
- 全身がだるい
- 筋肉痛がある
- 関節に赤みや腫れ、熱感を感じる
- 食欲がない
- 胸にサーモンピンク色の皮膚の異常が見られる
上記のような症状を放置するのは危険です。
発熱や風邪の症状を放置してしまうと、炎症が肺や耳などに達し、気管支炎や肺炎、中耳炎などの合併症が起こる可能性があります。さらに、別の病気が誘発されるリスクもあります。
特に、37.5℃以上の熱がある場合は、至急対処が必要な状況かもしれません。当院では、発熱や風邪の症状に関する診療に対応可能です。千代田区麹町周辺で発熱や風邪の外来をお探しの方は、当院までご相談ください。
当院の発熱・風邪症状外来の特徴
新型コロナウイルス感染症やインフルエンザに対応した診療
発熱・風邪症状外来では、これまで通り、発熱の患者様の治療に加えて、検査結果が陽性の患者様の治療や、入院が必要な患者様との提携にも対応しています。続いて、発熱・風邪症状外来での診療には「診察料や処方箋代」などが自己負担となる可能性がありますので、ご了承ください(3割負担の患者様の場合、約1,300円かかります)。
発熱患者様用の隔離室を完備
当院に受診される患者様のうち、発熱や風邪の症状がない方も多数いらっしゃいますので、当院では感染を防ぐためにも、発熱患者様用の隔離スペースを設けております。
徹底した感染防止対策
診察時にはガウン、手袋、フェイスシールドを着用し、感染防止に細心の注意を払っております。診察前後にはアルコール消毒などの対策を実施しており、感染の拡散を防ぐために努めております。
受診当日の主な流れ
1ご予約(※ご予約が無くても受診は可能です)
 患者様がすぐに受診いただけるよう、できる限りWEB予約をお願いしております。
患者様がすぐに受診いただけるよう、できる限りWEB予約をお願いしております。
予約をご希望の場合は、こちらよりご予約をお願いいたします。
2ご来院・受付
 ご来院いただいた際には、受付で診察券、健康保険証、またはマイナンバーカードをご提示ください。
ご来院いただいた際には、受付で診察券、健康保険証、またはマイナンバーカードをご提示ください。
(その他の医療証、紹介状、お薬手帳をお持ちの場合は、それらも合わせてご提示ください)
3隔離室へご案内
 受付が終わりましたら、発熱患者様用の隔離スペースまでご案内いたしますので、
受付が終わりましたら、発熱患者様用の隔離スペースまでご案内いたしますので、
お名前が呼ばれるまでお待ちください。
4診察・検査
 お名前が呼ばれましたら、診察室へお進みください。
お名前が呼ばれましたら、診察室へお進みください。
症状について詳しくお聞きします。
5お会計
 診察・検査が終わりましたら、再度隔離スペースにてお待ちください。
診察・検査が終わりましたら、再度隔離スペースにてお待ちください。
お名前が呼ばれましたら、受付にてお会計をお願いいたします。
発熱が関連する疾患
ウイルス感染症
37.5℃以上の発熱が1~3日持続し、喉の痛み、鼻水、咳、倦怠感などが起こります。これらの症状がある場合、ウイルス感染症(風邪)の可能性が疑われます。
細菌感染症
細菌感染症では、39℃以上の高熱や発熱が4日以上続く場合、より深刻な状態となる可能性があります。時にはウイルス感染症の可能性も考えられますが、まずは細菌感染症を疑う必要があります。
細菌感染症においては、熱が上昇する際に強い寒気や体の震えが現れ、特に高齢者の場合は、ぐったりする様子を見せるといった症状も現れることがあります。
2週間以上続く発熱
発熱が2週間以上続く場合、特殊なウイルスによる感染症、(高齢者の場合は)誤嚥性肺炎が頻繁に起きている状態、結核菌による感染症、膠原病、あるいは悪性腫瘍などの可能性を考慮する必要があります。
結核菌による感染症は、知らず知らずのうちに感染しているケースも少なくありません。
また、発熱や咳が何度もある場合は、レントゲン検査や痰の検査を受ける必要があります。
膠原病は、免疫の異常により、全身の血管や皮膚などに炎症が生じる疾患です。発熱・関節痛や皮疹が現れることが一般的ですが、初期段階では風邪のような症状しか現れません。発症から数週間経過した後に、他の症状がはっきりと現れることがあります。悪性腫瘍の中には、発熱が持続するタイプもあるため、微熱が1ヵ月以上続く場合は放置せず、さらに精密検査を受けることを推奨します。
発熱の際の対処法
発熱した場合、第一に原因を特定することが非常に重要です。新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ感染症などの感染症、悪性腫瘍(腫瘍熱)、膠原病などが疑われます。例えば、感染症により発熱している場合、そのままにしておくと全身に細菌やウイルスが広がり、敗血症という重い状態に陥る危険性もあります。そのため、放置せずに受診・検査を受けることをお勧めしております。
当院では、地域のかかりつけ医として、患者様が健やかに日々を暮らしていけるよう、今後も発熱などの感染症が疑われる方々の診察に取り組んでまいります。