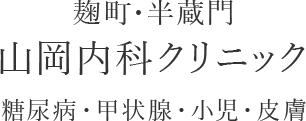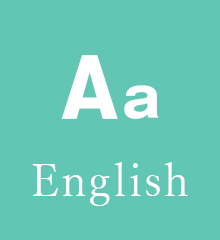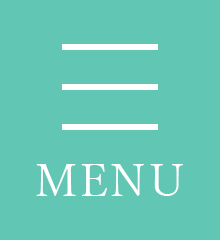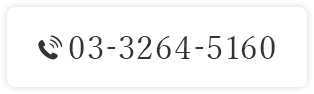HbA1cとは
 HbA1c(ヘモグロビン・エー・ワン・シー)は、健康診断の基本検査項目であり、血糖コントロールの状態を評価する上で非常に重要視されている数値です。ヘモグロビンとは、血液中の赤血球を構成するタンパク質を指します。
HbA1c(ヘモグロビン・エー・ワン・シー)は、健康診断の基本検査項目であり、血糖コントロールの状態を評価する上で非常に重要視されている数値です。ヘモグロビンとは、血液中の赤血球を構成するタンパク質を指します。
ヘモグロビンは、肺で酸素を受け取って全身へと運び、身体全体に酸素を供給する役割を果たしています。ヘモグロビンは血液中の糖と結びつきやすいタンパク質でもあります。
このため、特にブドウ糖と結びついたヘモグロビンの割合がHbA1cとなります。
血糖値とどう違うのか
糖尿病検査の際には、血糖値をチェックすることが一般的です。これは、血液中のブドウ糖濃度を調べて、糖尿病のリスクを評価するためです。
ここで、「血糖値」と「HbA1c」には何が異なるのかと疑問を感じる方もいらっしゃるかと思います。
血糖値は、最近の食事や運動によって急速に変動するものです。
そのため、血糖値は測定時によって大きく変動しやすい数値といえます。従って、空腹時血糖値や随時血糖値など、測定タイミングを正確に把握することが必要です。
一方、HbA1c値は、「赤血球の中のヘモグロビンに結合したブドウ糖の割合」を示す数値です。赤血球の寿命は約120日であり、その間にヘモグロビンはブドウ糖と結びつきます。これにより、過去1〜2ヶ月間の平均血糖値がHbA1c値と関連していることが実証されています。
そのため、最近の食事や運動の影響を受けずに、過去1〜2か月間の平均血糖状態を示す数値として、診断に活用されています。
HbA1cの正常値
HbA1cの正常な範囲は、日本糖尿病学会のガイドラインによると、「4.6〜6.2%」です。特定保健指導基準では、「5.6%未満」とされています。糖尿病学会によれば、
- 0〜6.4%:糖尿病の可能性が否定できません
- 5%以上:糖尿病の疑いが強い
とされています。
正常値は年齢や性別によって変わりますが、一般的には「5.5%未満」が正常とされています。
すでに糖尿病と診断された方は、重大な合併症のリスクを減らすために、HbA1c値を「7.0%未満」を目指す必要があります。
HbA1c値が高いと
糖尿病になる?
糖尿病についても解説
HbA1c値が高いと、一体
どうなるのでしょうか?
過去1、2か月の平均的な血糖の状態を示すHbA1cの値が高い場合、「継続して血糖値が高い」とされます。そして、その値が「6.5%以上」の場合、糖尿病の疑いが高まり、ブドウ糖負荷試験などの再検査が必要になります。
糖尿病とは
 本来、食事によって体内に取り入れられた炭水化物は消化され、血液中でブドウ糖に変化します。そこから、血液を通して体中に運ばれます。筋肉や臓器は主にブドウ糖をエネルギー源として利用しており、特に脳はブドウ糖のみをエネルギー源として使用しています。
本来、食事によって体内に取り入れられた炭水化物は消化され、血液中でブドウ糖に変化します。そこから、血液を通して体中に運ばれます。筋肉や臓器は主にブドウ糖をエネルギー源として利用しており、特に脳はブドウ糖のみをエネルギー源として使用しています。
炭水化物が摂取され、血糖として放出されると膵臓のランゲルハンス島からインスリンというホルモンが分泌されます。インスリンには、血糖を各組織に取り込んでエネルギーとして利用させたり、肝臓などでグリコーゲン合成を促進したりする機能があります。つまり、インスリンは血糖を迅速に処理することで、血中濃度を一定に保つ役割を果たしています。
何らかの理由でインスリンの働きが低下し、ブドウ糖の処理がスムーズにいかないと、血糖値が上昇しやすくなります。一定の基準を超えると「高血糖」と診断され、その状態が持続すると糖尿病と診断されます。
糖尿病の症状
糖尿病は「サイレントキラー」とも呼ばれており、初期段階では目立った自覚症状が見られません。ただ、尿に多量の糖が含まれるため、尿を出した際に泡立つことがあり、糖尿病に気づくこともあります。また、糖尿病を持つ方の中には、頻尿や多尿になり、喉が渇きやすくなることから水分摂取が増える傾向も見られます。
さらに、インスリンが不足して糖をエネルギーとして使えなくなると、体内のタンパク質や脂肪がエネルギー源として使われるため、体重減少や倦怠感に悩むケースもあります。糖尿病が進むと、全身の血管にも損傷が及ぶ可能性が高まります。特に糖尿病神経障害、糖尿病網膜症、糖尿病腎症などの重大な合併症が発症するリスクがあります。
糖尿病神経障害
糖尿病神経障害により、以下の症状が見られます。また、血行不良も起こりやすくなり、潰瘍や壊死のリスクも上昇します。壊死が進むと、最悪の場合、切除を余儀なくされます。
- 手足の痺れ
- 痛み
- 感覚麻痺
- 便秘、下痢
- 不整脈
- ふらつき
糖尿病網膜症
糖尿病網膜症では以下の症状を引き起こします。最悪の場合、失明してしまうリスクもあります。
- 網膜の血管からの出血
- 網膜細胞の栄養・酸素の
供給量が減る - 網膜剥離の発症
糖尿病腎症
糖尿病腎症は、血液中の蛋白が尿に漏れることで、蛋白が不足し、全身に浮腫みが現れます。さらに、水分が過剰になり、胸に水が溜まると呼吸が不十分になり、酸素を投与する必要が生じることもあります。
また、腎臓の糸球体が老廃物を濾過できなくなると、体外に老廃物を排出できず、人工透析が必要になります。透析が必要な原因の中で糖尿病が最も多いです。
その一方で、糖尿病は大血管の動脈硬化リスクが高く、脳卒中や心筋梗塞といった命に関わる重大な合併症が引き起こされる可能性があります。また、足の血流が悪化し、間欠性跛行症候群を引き起こすこともあります。
糖尿病の原因
糖尿病の主な原因は、「1型糖尿病」と「2型糖尿病」です。
1型糖尿病は、自己免疫などの問題によって発症します。膵臓の細胞が何らかの原因で損傷を受け、膵臓が生成するインスリンが減少することが発症の理由です。
一方、2型糖尿病は、生活習慣が原因で発症し、一般的に「生活習慣病」と呼ばれているものです。日本の成人の糖尿病の大部分は2型糖尿病です。
日本人は、遺伝的にインスリン分泌が弱い傾向があります。それに加えて、
- 炭水化物や高脂肪食の過剰摂取
- 運動不足
- 肥満
- ストレス
- 加齢
など
が糖尿病の引き金ともされています。また、内臓脂肪が増加した状態である「メタボリックシンドローム」でも発症しやすくなります。その他、妊娠、疾患、薬剤の副作用などが引き金となって糖尿病が発症するケースもあります。
HbA1c値が高いと
合併症の危険性があります
HbA1c値が高い状態は、血管に重大な損傷が与えられ続けている状態とも言えます。このことが、糖尿病を原因とする様々な合併症のリスクを増加させます。糖尿病の合併症は、微小血管障害、大血管障害、その他の障害に区分されます。
細小血管障害
- 糖尿病性網膜症
- 糖尿病性腎症
- 糖尿病性神経障害
大血管障害
- 狭心症
- 心筋梗塞
- 脳梗塞
- 閉鎖性動脈硬化症
その他の病気
- 糖尿病性足病変
- 歯周病
- 認知症
糖尿病性足潰瘍は、足の血管の狭窄・神経機能の低下により、潰瘍や感染症を発症しやすくなる疾患です。
「足の変形」「タコ」「壊疽」などが特徴とされていますが、糖尿病の患者様は感覚が鈍くなるため、傷に気付きにくく、症状が重くなりやすい傾向があります。
また、糖尿病は歯周炎や認知症にも悪影響を与えるリスクもあります。
HbA1c値が高いことで
考えられる他の疾患
HbA1c値は、糖尿病以外の疾患によって数値が上昇することもあります。糖尿病以外で疑われる疾患としては、「異常ヘモグロビン症」、「甲状腺機能亢進症」、「腎不全」などが挙げられます。
HbA1や糖尿病に関する
よくある質問
HbA1cが高いままにしておくとどうなるのでしょうか?
動脈硬化が進行し、脳梗塞・心筋梗塞・失明・腎不全(人工透析)・足の壊疽など、糖尿病の合併症が進んでしまいます。早くから治療と生活習慣を見直すことが重要とされています。
HbA1cが何%以上あると
糖尿病となりますか?
通常、HbA1cが6.5%以上で糖尿病と診断されます。しかし、空腹時血糖値や75gOGTT(糖負荷試験)などの結果を調べた上で判断されることがあります。
HbA1cを早く下げる方法
はありますか?
基本的には食事療法・運動・内服薬の継続が大切です。
しかし、日常生活において以下のポイントを意識するだけでも、一定の効果が得られる可能性があります。
- 朝、昼、夕食を一定の間隔で摂ること
- 夕食や就寝前の食事は控えめにすること
- 野菜など食物繊維が豊富な食品を積極的に摂り、食事の最初に摂ること
- 運動習慣を身につけること
- 睡眠不足をできる限り防ぐこと
- ストレスをできる限り避けること
ただし、医師の指導を受けながら生活習慣を改善することが最も有効ですので、少しでも懸念がある方は、ぜひ当院までご相談ください。
1〜2ヶ月で数値が改善する方もいらっしゃいます。
隠れ糖尿病のHbA1c
はどの程度ですか?
HbA1cが5.7〜6.4%の範囲は「糖尿病予備群」とされています。この場合は、いわゆる「隠れ糖尿病」の可能性があります。この段階で生活習慣を改善していけば、糖尿病の発症も予防しやすくなります。
HbA1cがいくつ以上の場合、
インスリン注射が必要になりますか?
典型的な場合、HbA1cが9%以上のとき、血糖コントロールが難しい方や急速に血糖値が上昇している方には、インスリン治療が選択されます。ただし、患者様の体調や合併症の有無によっても状況が変わります。
血糖値を下げるための食事の
優先順位はありますか?
血糖値の急上昇を予防するために、以下のような低GI食品が効果的だとされています
- 大豆製品(納豆・豆腐)
- 葉野菜(ほうれん草・小松菜など)
- 海藻類(ワカメ・ひじき)
- キノコ類(しめじ・しいたけ)
- 玄米・雑穀米
医師や管理栄養士と話し合いながら、バランスの取れた食事を意識しましょう。