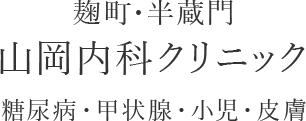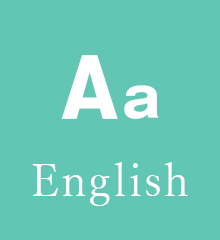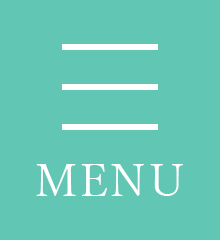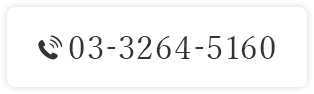脂質異常症とは
 脂質は細胞を構築する上で欠かせない要素であり、体のエネルギー源として機能します。食事から摂取された脂質は、中性脂肪(トリグリセライド)やコレステロールなどに変換され、細胞で利用される一方、不必要な部分は肝臓や筋肉に蓄積されます。
脂質は細胞を構築する上で欠かせない要素であり、体のエネルギー源として機能します。食事から摂取された脂質は、中性脂肪(トリグリセライド)やコレステロールなどに変換され、細胞で利用される一方、不必要な部分は肝臓や筋肉に蓄積されます。
コレステロールは、細胞に脂質を供給するLDLコレステロールと不要な脂質を回収するHDLコレステロールに大別されます。一部でLDLコレステロールを「悪玉」、HDLコレステロールを「善玉」と表現されることもありますが、この両者は本質的に重要であり、バランスよく機能していることが重要です。そのため、血中の脂質量が多い場合でも少ない場合でも、健康状態に影響を与える可能性があります。この状態を「脂質異常症」と呼びます。
特に、食習慣の乱れや運動不足などの生活習慣の乱れにより、中性脂肪やLDLコレステロールが増加し、HDLコレステロールが減少すると、血管に脂質が蓄積し、粥種ができて血管が激しく損傷します。
その結果、血管が損傷を受けやすくなるため、十分な注意が必要とされます。
コレステロールの
役割について
コレステロールは生きる上で欠かせない物質で、主に以下の材料として使用されます。
- 細胞の周囲を囲み、栄養素が細胞内に出入りする役割を担う細胞膜の材料
- 体内に取り込まれた脂肪の消化・吸収を促進する脂肪酸の基盤
- 血液中の水分や糖分、ミネラルを調節する副腎皮質ホルモンや性ホルモンの材料
脂質異常症の原因
脂質異常は、カロリーの高い食事、脂肪分の多い食べ物の過剰摂取、ビタミンやミネラル、食物繊維の不足など、食生活の乱れ、過度の飲酒、喫煙、運動不足などによる肥満などが引き金となっています。
脂質異常症の診断基準
| LDL コレステロール |
140mg/dl以上 | 高LDL コレステロール血症 |
|---|---|---|
| 120~139mg/dl | 境界域高LDLコレステロール血症 | |
| HDL コレステロール |
40mg/dl未満 | 低HDLコレステロール血症 |
| トリグリセライド | 150mg/dl以上(空腹時での採血) | 高トリグリセライド血症 |
| 175mg/dl以上(非空腹時での採血) | ||
| Non-HDL コレステロール |
170mg/dl以上 | 高Non-HDL コレステロール血症 |
| 150~169mg/dl | 境界域高Non-HDLコレステロール血症 |
※参考:
「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022版」
脂質異常症の種類
高LDLコレステロール血症
高LDLコレステロール血症は、血中LDLコレステロール値が過剰になる状態を指します。脂質異常症の中で最も多く見られるタイプであり、自覚症状はほとんど現れません。診断において、LDL値は極めて重要な指標です。
低HDLコレステロール血症
低HDLコレステロール血症は、何らかの原因により、血中HDLコレステロール値が低下してしまう状態です。生活習慣だけでなく、薬の服用や肝臓・腎臓などの病気など、先天的な要因が原因とされています。動脈硬化を引き起こしやすい種類とも言われています。
高トリグリセライド
(中性脂肪)血症
高トリグリセライド(中性脂肪)血症は、血中トリグリセライド値が高い状態を指し、炭水化物の過剰摂取、過度の飲酒、運動不足などが原因とされています。発症しても、それ特有の症状は現れません。動脈硬化だけでなく、膵炎などの原因としても挙げられます。さらに、高LDLコレステロール血症と併発するケースも決して少なくありません。
脂質異常症と動脈硬化
 LDLコレステロールが増えると、血管壁に付着してアテローム(粥状)が形成されます。この進行により、プラークと呼ばれる癌のような物質ができ、その部分で血流が制限され、血栓が生じやすくなります。また、その部位の血管は非常に脆弱になります。血栓が何らかの理由で剥がれて動脈内に流れると、肺動脈、冠動脈、脳へ流れる動脈などが詰まり、重大な障害のリスクが高まります。
LDLコレステロールが増えると、血管壁に付着してアテローム(粥状)が形成されます。この進行により、プラークと呼ばれる癌のような物質ができ、その部分で血流が制限され、血栓が生じやすくなります。また、その部位の血管は非常に脆弱になります。血栓が何らかの理由で剥がれて動脈内に流れると、肺動脈、冠動脈、脳へ流れる動脈などが詰まり、重大な障害のリスクが高まります。
一方、中性脂肪が過剰になると、LDLコレステロールの大きさが減少する働きをもたらします。それにより、血管壁への浸透性が高まり、動脈硬化を促進するリスクが上がります。このように、中性脂肪とLDLコレステロールは、相互に脂質異常を進行させる相関性があります。
HDLコレステロールが
高い場合は?
一般的に、HDLコレステロール値が高いと、冠動脈障害や脳血管障害のリスクが低くなるとされていますが、過剰になりすぎると、健康に悪影響を及ぼすこともあります。そうなると、血管障害のリスクを減らす効果は得られないと判明されています。
HDLコレステロールが増える原因は以下の2つが考えられます。
- 遺伝子の変化などにより、元々産生量が高いケース(原発性のもの)
- HDLコレステロールの生成プロセスとは関係のない、他の疾患によるケース(続発性のもの)
原発性の場合、遺伝子の急な変異によるHDLコレステロールの過剰産生や、除去の不足が挙げられます。
また、続発性の例としては、アルコールによる肝障害(肝硬変を伴わないもの)、甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、原発性胆汁性肝硬変などの疾患が挙げられます。
さらに、コルチコステロイド(副腎皮質ホルモン薬)、インスリン(糖尿病薬)、フェニトイン(てんかん薬)などによる副作用も考えられます。
脂質異常症の治療・予防
食事療法
 脂質や糖質の過剰摂取は、脂質異常の原因となります。まずは食生活を見直してみましょう。食べすぎ・飲みすぎを避け、脂肪分の多い食事を減らし、魚や豆類などのたんぱく質を摂取するように心がけましょう。ただし、1つだけを重点的に変えるのではなく、バランスの取れた食事を適量接種するように心がけましょう。
脂質や糖質の過剰摂取は、脂質異常の原因となります。まずは食生活を見直してみましょう。食べすぎ・飲みすぎを避け、脂肪分の多い食事を減らし、魚や豆類などのたんぱく質を摂取するように心がけましょう。ただし、1つだけを重点的に変えるのではなく、バランスの取れた食事を適量接種するように心がけましょう。
運動療法
 運動不足は肥満などに繋がり、脂質代謝を低下させます。ただ、いきなり激しい運動をすると、逆効果になる恐れもありますので、医師ときちんと相談しながら運動計画を立てましょう。ウォーキングなど負担の少ない有酸素運動や軽いスクワットなどの筋力トレーニングを継続できるように習慣づけましょう。
運動不足は肥満などに繋がり、脂質代謝を低下させます。ただ、いきなり激しい運動をすると、逆効果になる恐れもありますので、医師ときちんと相談しながら運動計画を立てましょう。ウォーキングなど負担の少ない有酸素運動や軽いスクワットなどの筋力トレーニングを継続できるように習慣づけましょう。
薬物療法
食事や運動を見直しても十分な結果が見られなかった場合は、薬物療法を検討することもあります。抗凝固薬、抗血栓薬、中性脂肪を減らす効果が期待できる薬、脂質の取り込みをブロックする薬など、患者様の病状に考慮しながら処方していきますので、お気軽にご相談ください。