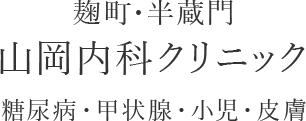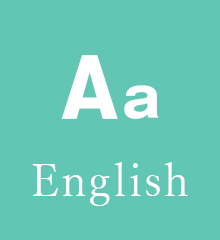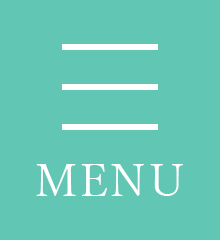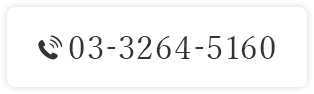糖尿病の治療法
 糖尿病の治療では、食事療法と運動療法がメインとされています。食事と運動療法だけでも、血糖コントロールがきちんとできる方も沢山います。
糖尿病の治療では、食事療法と運動療法がメインとされています。食事と運動療法だけでも、血糖コントロールがきちんとできる方も沢山います。
ただし、食事と運動療法だけでは血糖値が十分に下がらない場合や、血糖やHbA1cの数値が極めて高い場合には、内服薬やインスリン、GLP-1作動薬といった注射投与が選択されることもあります。
食事療法について
バランスの良い食事を
摂ることが基本
 糖尿病治療においてまず基本になるのは、食事療法です。食事療法の原則は、バランスの取れた栄養を摂取し、一日の必要エネルギー(カロリー)を超えないようにすることです。過剰なエネルギー摂取に気を付けながら、栄養バランスを整えることで血糖コントロールが改善され、合併症予防に役立ちます。
糖尿病治療においてまず基本になるのは、食事療法です。食事療法の原則は、バランスの取れた栄養を摂取し、一日の必要エネルギー(カロリー)を超えないようにすることです。過剰なエネルギー摂取に気を付けながら、栄養バランスを整えることで血糖コントロールが改善され、合併症予防に役立ちます。
また、食事療法を実践することで、糖尿病の発症を予防するだけでなく、同居しているご家族の将来の糖尿病リスクを軽減することも可能です。
糖尿病で食べた方がいい食品・
食べてはいけない食品はあるの?
「糖尿病にいいとされる食品」や「糖尿病に悪影響を及ぼす食品」という概念は存在しません。近年、インターネットの普及により、食事療法に関する情報が発信されていますが、誤った情報も少なくありません。どのような食品でも、過剰な摂取は健康に悪影響を及ぼす可能性があることをご留意ください。
糖尿病治療における
糖質制限食について
近年では糖質制限食(小麦を使った食品・お米などを摂らない食事制限方法)が人気ですが、筋肉が必要以上に落ちてしまったり、長期間続けることで糖尿病のコントールが悪化したりするリスクもあるそうです。さらに、寿命が短くなってしまうとも報告されています。
外来で患者様と食事についてお伺いすると、医師・栄養士などの食事指導を真面目に受け、色々と考えすぎてしまい「何を食べればいいか分からない」と迷ってしまう患者様もよくいます。食事は毎日行うので、「この方法でいいのかな?」と不安を感じる方もいらっしゃると思います。食事療法に関する疑問や不明点があれば、お気軽にご相談ください。当院では、1人ひとりに合った具体的で実践的なアドバイスを提供させていただきます。
運動療法について
当院の運動療法についての方針
糖尿病患者の方のための運動療法では、週に3回以上、中程度の運動(最大心拍数の50〜70%)を合計150分以上行い、週に2〜3回は筋力トレーニングも行うことが推奨されています。
具体的には、20分歩く(約2,000歩)だけで、糖尿病の管理指標であるHbA1cが約0.7%低下するという報告があります。運動不足や長時間座っている方ほど、将来の血糖コントロールにおいて、見通しが悪くなるとの研究結果もあります。また、最近の研究によると、40歳前後で体力が低かったグループは、高い体力を持つグループと比較して、将来の医療費が高くなる可能性があると指摘されています。つまり、運動は血糖値を改善するだけでなく、将来の病気リスクを減少させる可能性があると言えるのです。
「1日1万歩を頑張る!」など、具体的な目標を設定することも重要ですが、「座る時間を減らし、今よりも動くようにしよう」という考え方が当院の運動療法の基本です。
運動の効果
運動は、糖尿病の治療において重要な役割を果たします。
さらに、
- 降圧効果(血圧の低下)
- 脂質代謝の改善
(コレステロールや中性脂肪の改善) - 骨粗鬆症や筋力低下の予防
(寝たきりを防ぐ) - 免疫力向上
(多様な病気からの予防) - メンタルの健康
(不眠症やうつ病の防止) - 日常生活の質向上
など、科学的根拠が数多く示されています。近年では、がん疾患や認知症の予防においても、高い有効性があるのではないかと数多くの研究結果で報告されています。
米国スポーツ医学会は「Exercise is Medicine®」という言葉を商標登録しており、運動が健康長寿に繋がることを強調しています。糖尿病の治療だけでなく、日々の生活に運動を取り入れ、健康寿命を延ばしていきましょう。
具体的な運動方法
有酸素運動
有酸素運動は、ウォーキングやジョギングなどの活動を指します。 息が少し上がる程度で、気持ちよく続けられることを目指して実践しましょう。
レジスタンス運動
レジスタンス運動は、一般的に言われる「筋トレ」のことを指します。現在、日本は高齢化が進んでいます。寝たきりや介護予防の観点からも筋力を維持することは非常に重要です。糖尿病学会も、近年、筋肉や筋力の保持がますます重要だと認識され、筋肉の「貯蔵」という概念が注目を浴びています。
一部の患者様の中には、「運動」と聞くと緊張してしまうかもしれませんが、日常生活での家事や通勤、ストレッチやバランス運動も立派な「運動」になります。まずは有酸素運動から始め、日々の活動量を増やすことを目指して、当院で一緒に運動の習慣化に努めましょう。
ただし、運動療法は、制約や個々の健康状態に応じて中止すべき場合があるため、運動を開始する前には、問診、身体診察、検査の結果を確認し、患者様に合った運動方法を具体的にアドバイスして参ります。
内服薬
現在、糖尿病の内服薬は多種多様に存在しています。大まかに分けて、
- インスリン分泌を促すもの
- インスリンの効果を向上させるもの
(インスリン抵抗性改善)
が存在します。
近年では、血糖値を下げる効果が非常に高いとされる薬も登場しました。さらに、将来的には、細胞(ミトコンドリア)の品質を向上させ、血糖値を改善する薬も開発される予定です。ここ10年ほどで、安全で高い効果を持つ内服薬の種類が増加しており、治療法の選択肢が広がっています。内服薬の適切な調整により、以前はインスリン注射が必要な患者様でも、内服治療で済むケースが増えています。
当院の院長は、東邦大学医療センター佐倉病院、大橋病院において多数の糖尿病診療に携わってまいりました。その経験を活かし、内服治療を開始される際は、効果だけでなく副作用やライフスタイルへの影響にも配慮し、安心して継続できる糖尿病治療を心がけています。
インスリン療法について
 インスリンを自己注射で行う療法は、1型糖尿病において不可欠な治療法となっています。以前のインスリン治療では、開始までのハードルが非常に高く、事前の入院が必要とされることもありました。そのため、2型糖尿病の場合、他の治療方法が効果を上げない際の最終手段と考えられていました。
インスリンを自己注射で行う療法は、1型糖尿病において不可欠な治療法となっています。以前のインスリン治療では、開始までのハードルが非常に高く、事前の入院が必要とされることもありました。そのため、2型糖尿病の場合、他の治療方法が効果を上げない際の最終手段と考えられていました。
しかし、現在では、インスリン製剤や治療法が大幅に進歩し、インスリン療法の導入時には入院が不要となりました。2型糖尿病の患者様では、膵臓が疲弊しているため、この治療法によるインスリン補充は血糖値上昇を抑制するだけでなく、膵臓の仕事量を減らし、回復させるも期待できます。適切に実施することで、血糖値のコントロールが改善し、膵臓機能が回復するため、合併症の発生や進行を予防する効果が期待されます。
インスリンとは
インスリンは膵臓から分泌され、血液中のブドウ糖を臓器や筋肉に取り込ませる役割を果たします。また、グリコーゲンとして貯蔵することで、血糖値が上昇した際に適切なレベルまで下げることができます。
食事をすると、食後約1時間で血中のブドウ糖がピークに達しますが、インスリンが働いて徐々に血糖値を下げ、安定した状態に戻します。
インスリンの分泌が不足して、インスリンの働きが不十分になると、血糖値がうまく下がらなくなり、高血糖の状態が続いた結果、最終的に糖尿病を発症します。糖尿病は血糖値が常に高い状態になるため、血管への負担も増し、あらゆる重大な合併症を引き起こすリスクを高めます。
インスリン療法とは
インスリン療法は、不足分のインスリンを外部から補充する方法です。実際、何がインスリンなのか不思議に思う方も多いでしょう。
インスリンは、血液中のグルコース(血糖)を筋肉や肝臓、脂肪などの組織に栄養として取り込ませ、血糖を下げる唯一のホルモンです。通常、膵臓から分泌されたインスリンが適切に作用することで、血液中のグルコースを細胞活動のエネルギー源として使用し、余分なグルコースを肝臓、筋肉、脂肪に蓄えます。しかし、糖尿病を発症する場合、グルコースが適切に組織内に取り込まれず、余分な糖分が血液中に溢れて血糖値が上昇します。
内服薬だけでは血糖を適切に制御できない場合や、手術前など早急に血糖を下げる必要がある場合、または腎臓・心臓・肝臓などに持病があり、内服薬の使用が難しい場合には、インスリン注射が使用されます。
インスリン療法に対して、医師から「入院して行いましょう」と言われたり、患者様自身がためらう場合もあるかもしれません。
2型糖尿病の患者様においても、早い段階からインスリン治療を開始し、血糖値を改善することで、高血糖毒性を解除し、膵臓を休ませることができます。
それにより、膵臓が再びインスリンを分泌する能力を回復し、良好な血糖管理が可能となり、インスリン治療が中止できる可能性もあります。さらに、内服薬の量を減らすこともできるケースも多く見られます。
つまり、以前は糖尿病治療の「切り札」とされていたインスリン治療を適切なタイミングで導入することで、治療の効果を向上させることができるのです。
インスリン療法の主な種類
インスリン治療で使用される製剤には、持続型、中間型、速効型、超速効型があり、以下の4種が主に行われています。
これら4つの方法から、患者様の状態や生活スタイルに合わせて最適な選択を行います。
BOT療法
内服薬を継続しながら、1日1回、持続型インスリン製剤を注射する治療法です。この持続型インスリンは効果が徐々に現れ、長時間作用します。注射のタイミングは患者様が決めることができ、低血糖のリスクも低くなっています。インスリン治療を始める際に一般的に選択される方法です。
混合型インスリン製剤
による治療
中間型と超速効型または即効型を混ぜた製剤を1日1~2回注射します。配合比率が異なるため、血糖の動態を考慮しながら調整します。
追加インスリン療法(3回法)
毎食前に超速効型または速効型の注射を行う治療法です。食事前に注射するタイミングのため、1日に3回の投与が必要となります。
食事によって血糖値が上昇し、インスリンが分泌される自然な状態に近づける、生理学的な治療法とされています。
投与後は必ず食事を摂ることが欠かせず、食事が急にできない場合は低血糖を引き起こす可能性があるため、ブドウ糖を補給するなどの対応が必要です。
追加インスリン療法
(Basal-Bolus療法)
1日1回持続型のインスリンを投与し、超即効型または即効型を1日1~3回注射します。持続型は基礎分泌のインスリンを補う一方、超即効型または即効型は、食事などによる血糖値上昇に応じた追加分泌を担います。
入院せずにはじめられるインスリン療法
インスリン療法では、自己注射を行う必要があります。これまでは、手技や製剤管理を正確に行うために、1週間ほどの入院が必要でした。しかし、現在では、外来で医師の指導を受けることで、インスリン療法を始めることが可能です。
なお、ライフスタイルを考慮した上で、適切な製剤や投与方法を選び、外来で注射の手技、製剤の管理、血糖のコントロール、低血糖時の対処法などをしっかり学んでいただいてから、安定した治療を続けていくようお願いしております。