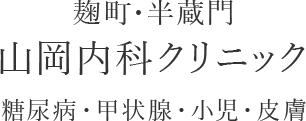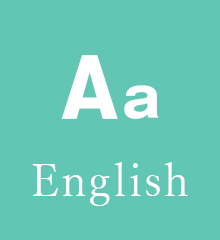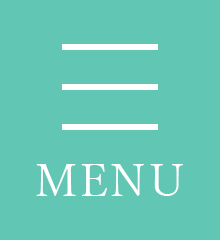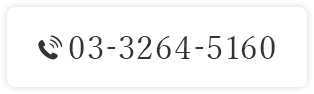糖尿病とは
 人体の主要なエネルギー源はブドウ糖です。血液中にあるブドウ糖は「血糖」として知られており、この血糖が過剰になると、全身の多岐にわたる組織に障害が生じる「糖尿病」になることがあります。
人体の主要なエネルギー源はブドウ糖です。血液中にあるブドウ糖は「血糖」として知られており、この血糖が過剰になると、全身の多岐にわたる組織に障害が生じる「糖尿病」になることがあります。
血糖値は膵臓から分泌されるインスリンによってコントロールされています。このインスリンが上手く働かなくなると、高血糖の状態が持続します。高血糖状態が長期にわたると、糖尿病を発症することがあります。
糖尿病に伴う三大合併症としては、腎臓障害や視力障害、神経障害などが挙げられます。これらを発症すると、より重大な状態へ進行する恐れもあり、最悪の場合、脳卒中や心筋梗塞などの深刻な疾患を発症する危険性も高まります。
糖尿病は、初期段階では自覚症状がほとんど現れません。ほとんどの場合、健康診断の結果などで指摘され、そこで判明します。疾病が進行して深刻になると、疲労感や体重減少、喉の渇き、頻尿、手足の先の痛みなどの症状が現れます。
糖尿病内科について
 近年、日本国内では糖尿病患者が増加しています。血糖値が高いまま放置していると、腎臓や神経障害、視力障害などの合併症を引き起こすリスクが高まります。糖尿病は自覚症状が乏しいため、発見が遅れ、適切な治療を受けずに合併症が進行してしまうケースも少なくありません。
近年、日本国内では糖尿病患者が増加しています。血糖値が高いまま放置していると、腎臓や神経障害、視力障害などの合併症を引き起こすリスクが高まります。糖尿病は自覚症状が乏しいため、発見が遅れ、適切な治療を受けずに合併症が進行してしまうケースも少なくありません。
当院には、糖尿病診療の経験豊富な医師による、早期発見と効果的な治療計画を提供しています。患者様に合った血糖値の管理と合併症の予防に取り組んでおりますので、健康診断などで血糖値・HbA1cが高いと言われた方もお気軽にご相談ください。
糖尿病に伴う合併症の評価を行います
糖尿病の初期段階では、自覚症状はほとんど現れません。健康診断で血糖値や尿中の糖の異常に気づくことが一般的です。
状態を放置すると、高血糖状態が長引き、次第に全身の微小血管に障害が生じ、病気が進行して合併症を引き起こします。
三大合併症(毛細血管の障害)
持続的な高血糖状態により、全身の微小血管に障害が生じます。初期段階では自覚しにくく、定期的な検査や健診で早期発見することが非常に重要です。
神経障害
神経障害は糖尿病の三大合併症の中で、初期に現れるものです。手足の末梢神経に障害が現れます。
知覚神経障害による手足の痺れや痛みが出現するのに加えて、傷や火傷による痛みも感じにくくなり、重症化しやすいという特徴もあります。
免疫力が低下し感染症にかかりやすく、下肢の壊死などが起こる可能性があります。自律神経障害も生じるため、発汗異常、めまい・ふらつき、筋力低下、筋肉の萎縮、胃腸の不調などの症状が生じるケースもあります。
網膜症
網膜症は、失明を引き起こす緑内障に次いで多い疾患です。網膜における毛細血管に障害が生じると、眼底出血や浮腫などの症状が現れ、網膜症が引き起こされます。初期段階では症状が自覚しにくいため、眼底検査などで診断されることがほとんどです。視覚に異常がない状態からでも、定期的な眼底検査を受けることが重要で、失明リスクを減らすには、早期発見と早期治療が欠かせません。
腎症
糖尿病によって少しずつ腎臓の微小血管も動脈硬化が進んでしまうと、腎機能障害が生じる恐れがあります。その結果、徐々に尿中に蛋白が排出されるようになります。腎機能が進むと最悪の場合、人工透析を余儀なくされる可能性があります。
感染症
糖尿病罹患により免疫力が低下し、白血球の活動が弱くなることで感染症にかかりやすくなります。皮膚感染症や尿路感染症、肺炎などに罹患し、それらが悪化すると、最悪の場合命を落とす恐れがあるため、注意が必要です。
心・脳血管障害(心筋梗塞・狭心症・脳梗塞・脳出血などの大血管の障害)
毛細血管に加えて、太い血管の閉塞が起こると、心臓や脳の血管が詰まります。その結果、心筋梗塞や狭心症、脳梗塞、脳出血などが発症します。心臓や脳の血管に加えて、下肢の動脈が閉塞性動脈硬化症を引き起こすと、下肢の壊疽などの深刻な合併症などをもたらす恐れがあります。
その他の合併症
その他の合併症としては主に、皮膚病が挙げられます。当院では、患者様の状態に考慮しながら血液や尿検査、心電図検査などを実施し、早期発見と適切な治療を提供しております。
糖尿病の治療
生活習慣を改善していくため、食事療法や運動などに取り組んでいきます。患者様1人ひとりに合った治療方針を提案しており、薬物療法が必要な場合は、病状・年齢・ライフスタイルなどを考慮しつつ、最適な治療法をご提案しています。
生活習慣病に関連する高血圧など、他の疾患がある場合も、同時並行的に治療を行って参ります。
糖尿病療養指導
治療中、患者様の目標やモチベーションを維持できるよう、患者様のご相談に丁寧にお応えし、サポートしていきます。
また、必要な方には、血糖値の測定方法やインスリンの注入方法なども詳しく説明させていただきます。
糖尿病療養指導
- 血糖値の測り方
- 低血糖に関する指導
- 普段の過ごし方
- インスリン注射方法
- 生活での疑問・ご相談事
など
HbA1c値と合併症
赤血球内に存在するヘモグロビンと血糖が結びついてできるのが「HbA1c(ヘモグロビン・エー・ワン・シー)」です。ヘモグロビンと血糖は早く結合するため、血糖値の高い状態が続くと、HbA1c値も上昇します。このHbA1cの高い状態が続くと、血管障害が進行し、糖尿病網膜症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症などの三大合併症を招きます。
さらに、動脈硬化の進行により、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血、閉塞性動脈硬化症などの大きな血管障害が発症する危険性があります。
また、歯周病、認知症、糖尿病性足病変なども、糖尿病に由来して悪化すると指摘されています。こうした糖尿病による合併症を予防するためにも、HbA1c値をコントロールすることが重要です。当院では迅速HbA1c測定機を導入しているため、数分で数値が分かります。
よくある質問
健康診断で血糖値について指摘されましたが、診察をしていただけますか?
当院では、企業健診などで指摘を受けた方向けの診察も行っております。糖尿病・高血圧・脂質異常症が当院の専門分野となっております。検査結果を持っていただいた上でご来院いただければ、より専門的な検査も可能です。
糖尿病が心配なのですが、血液検査の結果はすぐに分かりますか?
当院では、院内で糖尿病関連の血液検査を迅速に解析しております。血糖値やHbA1cの結果はその場で分かりますので、すぐにお伝えできます。
糖尿病に対する薬物療法では、通常、どのような薬が使用されますか?
糖尿病治療には、内服薬と注射薬の両方が用いられます。内服薬には、主にインスリン分泌を促進する薬や、インスリン機能を改善する薬、尿中の糖の排出を促す薬、血糖値を下げる薬、血糖値の急激な上昇を防ぐ薬などが存在します。一方、注射薬には、GLP-1受容体刺激薬、GIP/GLP-1作動薬、インスリン製剤などの種類があります。患者様の病状や年齢、腎臓の機能、肥満度、合併症の有無などを考慮し、最適な薬を選択していきます。
糖尿病と診断された場合、受けるべき検査は何でしょうか?
糖尿病の診断を受けた方には、血糖値やHbA1c値が正常範囲に収まっているかをチェックするために、血液検査を受けていただく必要があります。特にHbA1c値が高い場合には、定期的な血液検査が必要となります。さらに、尿検査や心電図検査なども行い、合併症を早期に発見することが大切です。