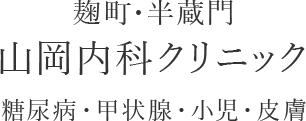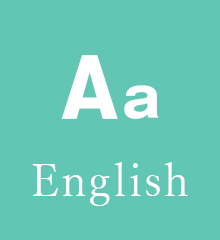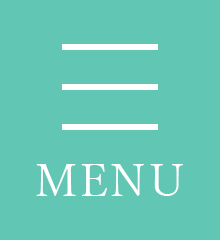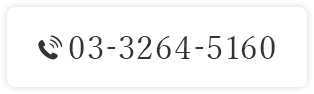糖尿病が引き起こす合併症とは
 糖尿病がもたらす3大合併症には、神経、腎臓、目などへの損傷が含まれます。また、糖尿病は脳卒中や心臓疾患など、命を脅かす疾患につながる動脈硬化のリスクを高めると言われています。
糖尿病がもたらす3大合併症には、神経、腎臓、目などへの損傷が含まれます。また、糖尿病は脳卒中や心臓疾患など、命を脅かす疾患につながる動脈硬化のリスクを高めると言われています。
症状がなくても、悪化している可能性があるため、早めの対処が必要です。血糖値を確実に管理して、症状の進行を防ぎましょう。そして、医師のアドバイスを受けながら治療を受け、血糖コントロールに努めましょう。
糖尿病の3大合併症
糖尿病神経障害
この障害は、高血糖状態が持続することで、手足の神経に損傷が起こり、手指や足先、裏側などに痺れや痛みが生じる病気です。症状は両手・両足で対称的に現れ、長期間の痛みも特徴の1つです。
症状の悪化により、感覚が低下し、足の壊死や潰瘍が生じるリスクがあります。気になる症状がある方は、速やかに医師へ相談してください。
主な症状
下記の症状が糖尿病の治療中に出た場合、早めにかかりつけの医師に相談しましょう。
これらの症状は主に、足の指先や足の裏、手の指先などに起こります。
- チクチクするような痛み
- うずくような痛み
- ヒリヒリした痛み
- ジンジンした痛み
- ピリピリした痛み
- 焼けるような痛み
- ズキズキするような痛み
- 手足の痺れ
など
糖尿病網膜症
糖尿病網膜症は、血糖値が高い状態が続くことで、目の網膜内の血管に障害が生じる疾患です。目立った症状は見られず、進行する過程で重症化し、最悪の場合、失明のリスクがあります。病状を進行させないためにも、早期に異常を見つけて治療を受けることが重要です。心当たりのある方は年に1回以上の眼底検査を受けるよう心がけましょう。
主な症状と進行段階
初期段階では、症状が現れないことが一般的で、目の中で軽度の出血が見られる程度の異常が生じます。段階的に進行すると、目の血管に閉塞が生じ、視界がかすむなどの症状が起こります。さらに悪化すると、目の内部出血が増加し、緑内障や網膜剥離など他の疾患が発症する可能性があります。また、飛蚊症や視力低下が起こり、状態が悪化すると失明する恐れがあります。
糖尿病腎症
糖尿病腎症は、持続的な高血糖状態により、腎臓内の血管に損傷が生じる疾患です。腎臓の機能が次第に低下し、最終的には尿排泄が困難となり、透析療法を余儀なくされます。初期段階では目立った症状が見られないため、病態が進行してしまうことがあります。そのため、腎臓の機能や尿の検査を定期的に受けて、早期に異常を発見することが重要です。
主な症状
最初は症状を感じないケースも多いですが、徐々に尿中のタンパク質が増加し、体がむくみやすくなります。腎臓の機能が低下し、腎不全が発症すると、貧血、息切れ、全身のだるさ、食欲不振などの尿毒症症状が起こります。これらは、高血圧や慢性腎炎から発展した腎不全と同様の症状です。
その他の合併症
糖尿病の方は、毛細血管の損傷以外に、大血管の閉塞にも繋がりやすい動脈硬化を起こす恐れもあるため、動脈硬化の発症には十分に気を付けなくてはなりません。
大血管障害
- 心筋梗塞や狭心症
- 高血圧
- 動脈硬化
- 脳梗塞
- 脳卒中
- 閉塞性動脈硬化症(足の切断を
余儀なくされる恐れもある)
など
その他感染症など
- 気管支炎
- 水虫(白癬)
- 膀胱炎、腎盂炎、尿道感染症
- 歯周病
- 肺炎
- できもの
など
糖尿病の3大合併症は
どの順番で発症する?
糖尿病の3大合併症は「糖尿病神経障害」→
「糖尿病網膜症」→「糖尿病腎症」の順番で
発症するケースがほとんどです。
合併症の出現する時期は?
糖尿病神経障害(神経の問題)や、糖尿病網膜症(視力の問題)は、糖尿病発症後5~10年で現れることがあります。一方、糖尿病腎症(腎臓の問題)は、10~15年後に現れることが一般的です。
さらに、高血圧や高脂血症が重症化し、動脈硬化が悪化すると、突然脳梗塞や心筋梗塞、壊疽(えそ)などの合併症が発症するリスクもあります。
糖尿病が疑われる場合の検査
糖尿病かどうかを確認するためには、いくつかの検査を組み合わせて行います。特に、血糖の状態や過去の血糖コントロールの指標、腎機能の状態を把握することが重要です。
問診
糖尿病は症状を自覚しにくい疾患ですが、診察では症状だけでなく、過去の病歴や生活習慣、ライフスタイルなど、幅広い情報をお聞きして診断や治療に役立てていきます。
主な問診項目
- 自覚症状の有無と具体的な症状、
起こり始めた時期など - 過去の病歴の有無、その内容
- 服薬中の場合は、服用中の薬剤
- 健康状態や体重の変化
- 糖尿病の血縁者の有無
- ご家族に糖尿病の方が
いらっしゃるか - 喫煙や飲酒の有無、摂取量や頻度
- 運動習慣の有無
- 食習慣や嗜好品
- 普段のライフスタイル
- ストレスの有無
など
血液検査
 採血により、現在の血糖値やHbA1cの状態を調べることができます。
採血により、現在の血糖値やHbA1cの状態を調べることができます。
当院では血糖値やHbA1cは数分で検査結果が分かります。
必要に応じて、血中のインスリン、C-ペプチドもあわせて確認します。
血糖値の測定
血糖値は、血液中のブドウ糖の濃度を表す数値で、糖尿病の診断に欠かせない基本的な検査項目です。空腹時の血糖値に加え、食後2時間後の血糖値も測定することで、インスリンの分泌や働きに異常がないかを評価します。
基準値
空腹時血糖
- 正常値:100mg/dl未満
- 正常高値血糖:100~109mg/dl
- 予備軍型:110~125mg/dl
- 糖尿病型:126mg/dl以上
食後血糖
- 正常値:140mg/dl未満
- 予備軍型:140~199mg/dl
- 糖尿病型:200mg/dl以上
HbA1c
(ヘモグロビンエーワンシー)
HbA1cは、過去1~2か月の平均的な血糖状態を示す指標です。この値は検査前の食事に影響されないため、糖尿病の診断や治療効果の確認において非常に重要な役割を果たします。
基準値
- 正常値:6%未満
- 予備軍型:6~6.4 %
- 糖尿病型:5 %以上
尿検査
糖尿病が進行すると腎臓に負担がかかることがあります。尿検査では、尿中のアルブミン量を調べることで、腎機能の低下が始まっていないかを確認します。健康な状態では、アルブミンは尿にほとんど排出されませんが、腎臓が障害を受けると数値が上昇する傾向にあります。
基準値
- 正常値:30 mg/gCr 未満
- 早期腎症:30~299 mg/gCr
- 顕性腎症:300 mg/gCr %以上
糖尿病と診断された方
に行う定期検査
(合併症予防のための検査)
糖尿病と診断された後は、ただ血糖値をコントロールするだけでなく、合併症を未然に防ぐことが治療の大きな目的となります。
糖尿病は血管や神経、腎臓、眼などにさまざまな影響を及ぼすため、治療開始後も定期的に合併症の有無を確認する検査が重要となります。
血管の検査
糖尿病によって引き起こされる合併症の多くは、血管障害と関係があります。動脈硬化の進行具合や血流の異常を早期に把握するための検査が推奨されます。
頸動脈超音波(エコー)検査
 首の左右にある太い血管「頸動脈」を超音波で観察し、血管壁の厚さ(IMT)やプラークの有無、血流の状態などを確認する検査です。脳梗塞などのリスクを調べるために有用とされており、動脈硬化の進行度を視覚的に評価できます。
首の左右にある太い血管「頸動脈」を超音波で観察し、血管壁の厚さ(IMT)やプラークの有無、血流の状態などを確認する検査です。脳梗塞などのリスクを調べるために有用とされており、動脈硬化の進行度を視覚的に評価できます。
心臓の検査
糖尿病は心筋梗塞や狭心症などの心疾患の発症リスクを高めることが知られています。心臓の機能やリズムに異常がないかを確認するための検査も重要です。
心電図検査
心臓が発する電気信号を記録し、不整脈・狭心症・心筋梗塞などの兆候を早期に発見します。高血圧や動悸などの症状がある方には特に推奨される検査です。
腎臓の検査
糖尿病によって腎臓に障害が起こる「糖尿病腎症」は、放置すると人工透析が必要になる深刻な合併症です。自覚症状が乏しいため、定期的な検査で早期に兆候をとらえることが重要です。
尿中微量アルブミン検査
尿に微量なアルブミンが排出されていないかを調べます。ごく初期の腎障害でも検出が可能で、糖尿病腎症の早期発見に最も有効な検査のひとつです。
アルブミンの基準値とリスク分類
- 正常値(第1期):30 mg/gCr 未満
- 早期腎症(第2期):30~299 mg/gCr
- 顕性腎症(第3期):300 mg/gCr 以上
早期であれば、適切な治療により腎機能を正常域に戻すことも期待できます。
尿蛋白検査
腎機能がさらに進行すると、一般的な尿検査でも蛋白尿が検出されるようになります。1日の尿蛋白量が150mgを超える場合、「異常」と判定されます。定期的な検査で進行を抑えることが可能です。
目の検査
眼底検査
糖尿病網膜症は、糖尿病による三大合併症の一つで、進行すると視力低下や失明の原因にもなります。眼底検査では、眼球の奥にある網膜の血管の状態を調べることで、初期の変化を捉えることが可能です。目のかすみやまぶしさなどの症状が現れる前から、定期的なチェックが推奨されています。